SNS上での女性へのいやがらせから、ヒラリーなど女性政治家への反感、女性を標的にした無差別殺人まで、それらの背後にある統一的な概念とはなんなのか、説明できるようにしてくれる本である。
その概念がミソジニーである。ミソジニーは女性嫌悪あるいは女性憎悪という意味だとされている。ミソジニストとは女性が女性であることで憎悪する人間だということになるが、そんな人間はほとんどいないことに気づく。女性に嫌がらせをしたり殺傷する男も、母親や姉妹や妻や娘を愛している。するとその男をミソジニストとは呼べなくなってしまう。
だから著者はミソジニーという語の意味を改良することを提案する。著者によれば、ミソジニーとは、「女性は男性をサポートし敬愛し癒しを与えるべきである」と考える人たちによって、そんな妄想的なルールに違反する女性を罰するものである。
「女性は男性に仕え、男性にはそうされる当然の権利がある」と考える家父長制にとって、性差別主義は家父長制的秩序の「正当化」部門(男性は生まれつき女性より優れているのだ、などという偽科学で理論武装する)であり、ミソジニーはルールを破るものを取り締まり罰を与える「法執行」部門である。
政治や学問などいままで男性が権力を独占していた領域に女性が入ろうとすると、女人禁制の場所に侵入した罪、あるいは男性のものを奪おうとした罪によって男性たちの怒りを買い、罰せられることになる。
また、女性が男性に優しくしなかったり(たんに笑顔を見せなかったり)、リスペクトを示さなかったり、面倒をみなかったりすることは、女性の当然の義務を怠ったとみなされたり、男性の愛されケアされる権利(そんなもの実在しないのだが)を奪ったという罪によって罰されることになる。
著者はそんな論理の発動する力学(ダイナミクス)を、SNS上のいやがらせから殺人事件、ヒラリーとトランプが戦った大統領選などを例に取り上げ、心理学実験や統計などのデータを示しながら、男たちがいったい何に腹を立て、彼らの行動の背後にどういう論理があるのか明快に説明されて、とても説得力がある。
女性だけじゃなく性的マイノリティや民族的マイノリティに向けられる憎悪(ヘイト)にも同じような力学が働いているのかもしれないと著者は説く。そういった憎悪は、対象を非人間化していることによって生じるのだと理解されることがあるが、実は自分たちと同じ人間だという認識が憎悪の前提になっている可能性がある。自分たちと同等の権利を持つ存在だからこそ、自分たちの権利が奪われるという恐怖になりそれが憎悪を生む。だとしたら、マイノリティも同じ人間なのだと認識させても差別の解消にならない。自分たちには彼らを抑圧したままにする権利などないのだと認識を変えさせるしかない。『ハックルベリー・フィン』の読解がとても興味深い。カミュ『異邦人』で一人で行動している女性が男性の登場人物からはロボットに見えるという部分も印象深い。
「第6章 男たちを免責する」の内容は映画『プロミシング・ヤング・ウーマン』の内容そのままで(原著が出たのが2018年、映画は2020年公開)、アメリカではベストセラーになったらしいから影響があったのかもしれない。
トランプが大統領選に勝った後ということもあり、著者はほとんど絶望しミソジニーをなくすにはどうしたらいいかわからないと白旗を上げる。しかし、男のものとされる領域に入ろうとする女性への批判にはジェンダー・バイアスが働いているかもしれないことやミソジニーのロジックを一人ひとりが意識し指摘できるようになれば、すくなくともそれに加担することはなくなるんじゃないだろうか。そうなれば、大統領選でヒラリーが左派の男性や白人女性からもバッシングを受けたようなことはなくせるかもしれない。
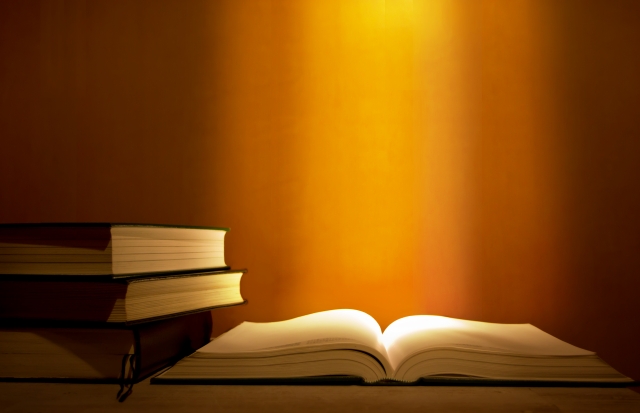


コメント