決定論と自由は両立するか、両立論と非両立論とそれぞれに対する反論を網羅的に紹介、検討していく。日本では単著が翻訳されていないような哲学者の考え方も詳しく紹介されていてよかった。
自由の必要条件としての他行為可能性モデル(他の選択肢もとりうる可能性がなければ自由とはいえない)と源泉性モデル(フランクファートの「二階の意欲説」)。決定論と自由は両立するという両立論はいつも責任と道徳の話になるので、だんだんつまらなくなってきた。自由論の本だとお決まりの内容だからというのもあるのかもしれない。
同時に読んだ『哲学がわかる 自由意志』のトーマス・ピンクの考えは、非因果説なんだな。非因果説はこの本では簡単にしか紹介されていないが、興味が出てきた。
世界は決定論的だとしか思えないけど、その一方で日常生活ではピンクが論じるような「自由」を感じる。ピンクはホッブズの考え方を否定してるから、決定論と非因果説は両立しないんだろうけど、やっぱりそうなんだろうか? 非因果説「非因果」が指すのは、行為の「決心」を引き起こす原因のようなものがない、ということで……頭がかゆいから頭を掻く、とか、おなかが減ったから食事をする、とか欲求によって行為が引き起こされたと考えるのではなくて、かゆみを解消するために頭をかくとか空腹を満たすために食事をするというように考える……しかし、これって行為の捉え方を変えただけで客観的にみればまったく同じ行為なんじゃないだろうか。たとえば、ある行為に結びついた脳内現象がすべてトレースできて確認できるような機械が発明されたとしたら、非因果説者も「自由」があるとは考えられなくなるんだろうか。
決定論的世界に生きる人もあらゆる選択において「自由」を感じるんじゃないだろうか。というか、それがこの現実のありかたなんじゃないかと思ってるけど。非因果説、非両立論を信じるリバタリアンからすると、決定論的世界に生きる人間の行動は非決定論的世界に生きる人間の行動と客観的には何も変わらないけど、自由意志版の哲学的ゾンビということになるんだろうか。
本書の最終章は、自由と責任との関係だけでなく、もし自由がなければ人生の意味や愛といった概念はどうなるのかという点が論じられていて興味深かった。まさにそういうことを探求した映画が『TENET』だったんじゃないだろうか。決定論的な世界で人は「主人公」たりうるのか、愛とはどういうものでありうるか。
次は、非因果説を論じた本と自由と責任以外の概念の関係について論じた本を探して読んでみよう。
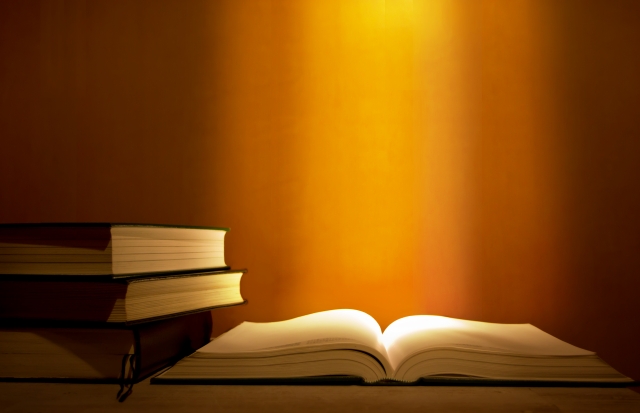


コメント