大学で英文学を教えている40代の著者が総合格闘技に挑戦して実際にリングに立ち対戦するまでのルポルタージュと、格闘技や暴力についてのエッセイ。
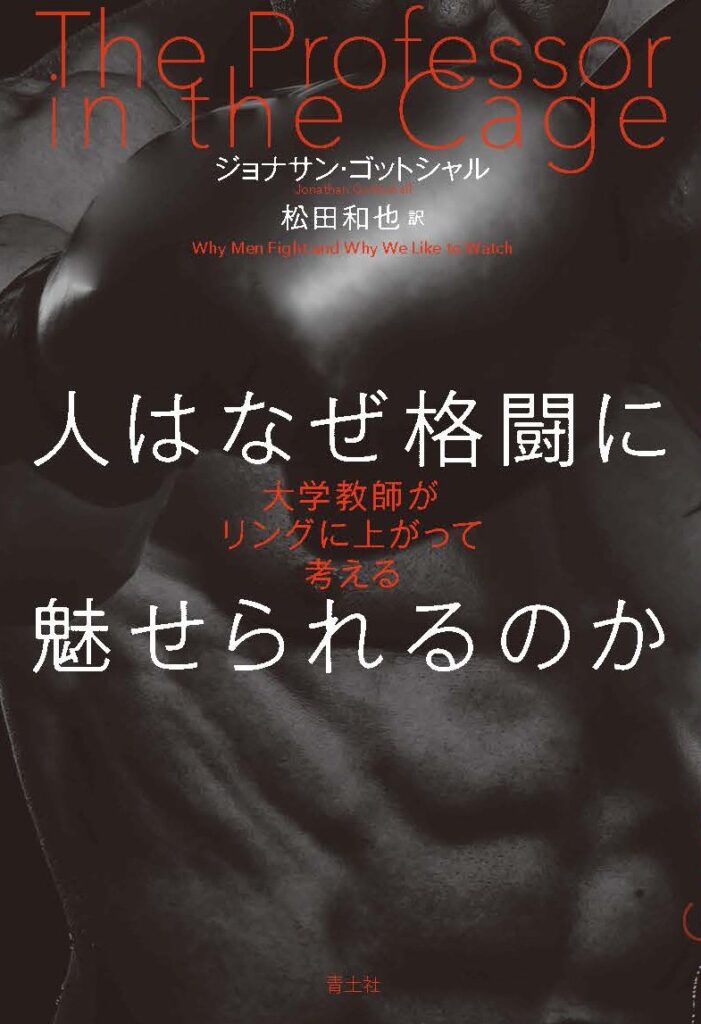
ボクシングなど1対1で対戦するスポーツの形式、ルールなどが決闘にルーツをもつこととか、総合格闘技のトレーニングの体験やそこで出会った人々についてなど、おもしろい部分もあるのだが、いわゆる「男らしさ」を称揚し、「女々しい」とか「オカマ」という言葉を侮蔑的に無批判に使っていて、なかなか読むのが苦痛になるところも多かった。
進化生物学を根拠に性差別的な現状を肯定しているところは最悪で、まるっきりインセルに人気のインフルエンサーの書いた文章としか思えないところも多かった(me tooムーブメント直前の2015年出版で、翌年にはトランプが大統領になっている)。この著者じつはヤバいやつなんじゃないかと途中で不安になって、検索して確かめてしまった。インセルのオピニオンリーダーではないみたいだけど、最新刊はニューヨーク・タイムズの書評で酷評されたらしい。
著者は様々な文献や論文を引用して、現代の男子大学生の行動や格闘技をチンパンジーなどの動物の行動と結び付け、戦争から男女間の賃金格差まですべてを進化生物学的に説明しようとする。
性差研究の最前線からのメッセージ ―進化・文化論争は超えられるか―
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjpr/60/1/60_95/_pdf
著者(ゴットシャル)の説明に反して、最近の研究では攻撃性にみられる性差については証明されてるとはいえず、言語能力、空間能力、男性的性格特性、女性的性格特性なども性差より個人差のほうが大きいらしい。また、「男女平等の達成度の高い国(収入や職種における男女差の小さい国)では,配偶者の選択における進化生物学的な予測にもとづく男女差(e.g.,男性は女性に若さや家事能力を求め,女性は男性に地位や経済力を求める)はあまりみられないとの報告」もあるらしい。このPDFで紹介されている学説が正しいのか自分には判断できないが(そういう意味ではゴットシャルも英文学の教師であり、理系の専門家ではない)、なんでもかんでも生物学的性差で説明しようとするのは雑すぎるだろうということはわかる。
「戦争ゲーム」という章では、フットボールなどのチームゲームは戦争のための訓練・予行演習なのか、それとも戦争を避けるためのものなのかという問いを立て、「どちらでもある」と答えている。古代の部族間の戦争はともかく現代の国家間の戦争とフットボールを結び付けて論じるのもやはり雑すぎじゃないだろうか。
格闘技やスポーツやそのファンは残酷で野蛮だと書いたかと思うと、別のところでは、現代の格闘技がスポーツとしていかにソフィスティケートされているか、MMAの選手や観客は礼儀正しくおとなしいか書かれていたりする。結局、格闘技やスポーツ、「男らしさ」とは野蛮なものなのか崇高なものなのか。著者は「両方だ」と答えるかもしれないが、混乱しているようにしかみえない。現代社会・文化と「男らしさ」の良い面と有害な面の関係を論じるにはこの本は短絡的すぎるのだ。
力の強いものが尊敬され、男同士は強い絆でつながり、強い男が「イイ女」を手に入れる……ゴットシャルは総合格闘技のジムでの絆を男だけのユートピアのように書いていて、昔の男社会は社会全体がそのようなものだったのかもしれない。しかし、現代社会ではもはやそのようなユートピアは男性のファンタジーの中にしか存在していない。
生物学的な「男らしさ」にはリスクを進んで取りにいったり、競争的だったり、良い面もあるのだろうが、その反面、酒場で目が合っただけで喧嘩になったり、喧嘩に負けることに怯えて体を鍛えたり、横断歩道のない所で道を渡ろうとして車にはねられたり(女性より男性のほうが何倍も多いらしい)、戦争に行く羽目になったりするというのであれば、「男らしさ」は呪いのようなものでしかないのではないだろうか。
この本を読んだのは、 映画における暴力――銃撃戦や血みどろの殴りあい――とはなんなのか、なぜ作られなぜ観客は求めるのかについて考えたくて読んだのだが、まさにこの疑問に直接答えてくれているところがあった。著者による答えは本を読む前から漠然と考えていたものと同じだった。「ポルノと同じ」。実際、著者が初めてUFCのビデオを観たときの体験を、初めてポルノビデオを観たときのことと重ねている。他人がセックスしているのを見て興奮するのと同じように、他人が殺しあうさまを見ると興奮するのだ。脳内で起こっていることはそういうことなのだろうけど、「ポルノである」という答えでは満足できない。ヘミングウェイは闘牛について『午後の死』を、ジョイス・キャロル・オーツが『オン・ボクシング』を書いたように、まだまだ考察すべきことがあるはずだ。
暴力的な映画を観たりスポーツをすることで暴力衝動が減るというカタルシス理論もやはり科学的には立証されていないらしい。ホラー映画で感じる恐怖、アクション映画のハラハラするアクションなどは観客にアドレナリンを出させるポルノ的要素なのは確かだ。しかし映画の中であるいは現実で殴りあい血みどろになる姿には、それだけではない何かがあるのではないかと感じる。
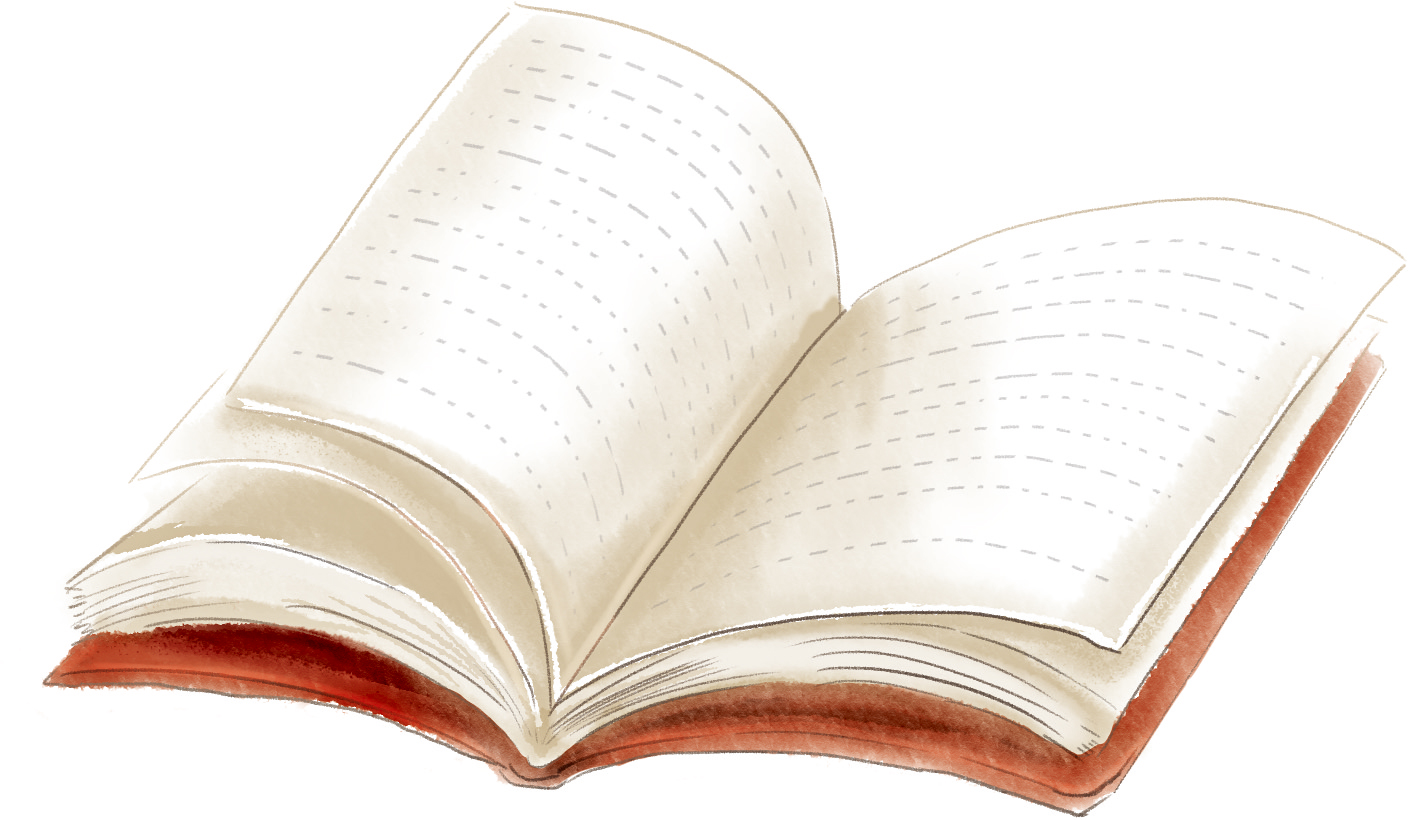


コメント