デヴィッド・フィンチャー監督、マイケル・ファスベンダー主演。
いままで一度も失敗したことがない凄腕の殺し屋である主人公だが、暗殺に失敗したことで逆に命を狙われることになる。巻き添えで暴行を受け重体になった恋人の復讐と身の安全のため、自分を狙った実行犯と依頼主を探し出そうとする――という筋立てだけをみれば同じような映画はいっぱいある。しかし、本作はとにかく低体温で、主人公が泣いたり怒鳴ったりすることはいっさいない。最初から最後まで人生哲学かビジネスの啓蒙書のような言葉をひたすらつぶやき続ける。
主人公はマントラのように「感情移入するな。感情移入は弱さを生む」と繰り返す。自分や恋人以外の人間の命についてはひたすら冷淡で、暗殺が社会にどういう影響を与えようがどうでもいいと考える主人公はあまりに利己的で、観客もこの主人公には感情移入できないだろう。しかもそんな虚無がバイオレンスと結びついていて殺伐とした気分にさせられる。
自分を厳しく律する主人公のように、この映画は禁欲的で、快楽を提供してくれるファンタジー要素がほとんどない。たとえば他のアクション映画にならありそうな、エキゾチックな風景や美女とのロマンス、派手な銃撃戦やカーアクション(例外は、ティルダ・スウィントンのシーンに出てくる料理とウィスキーくらいだろうか。しかし主人公はウィスキーを1杯飲むだけで料理にはいっさい手を付けない)。善が勝ち悪が滅びるという物語もそういうファンタジーのひとつなのかもしれない。人をばんばん撃ち殺しながら享楽的な映画よりは、ある意味で倫理的といえるのかもしれない。
主人公は謙虚でもある。一流の暗殺の腕を持っているのに、自分は天才ではない、一握りの人間ではなくありふれた人間であると自認している。運命などなく、一瞬先に起こることも予測できない。彼は狂人ではない。どこまでも現実的で”正気”だ。そのことにまた暗澹とした気分にさせられる。
映画の冒頭で主人公が思い出せなかった「汝の意志することを行え」と言った人物とは神秘家のアレイスター・クロウリーのことかもしれない。クロウリーは「汝の意志することを行え」という哲学について次のように語っている。
各人は以下の権利を有する。 自分自身の法によって生き、 自分の意志するやり方で生き、 自分の意志するままに働き、遊び、休息し、 自分の意志する時に自分の意志する方法で死に、 自分の意志するものを飲食し、 自分の意志するところに住み、 自分の意志するままに地上を動き回り、 自分の意志するままに考え、話し、描き、塗り、彫り、刻みつけ、型取り、建て、服を着、 自分の意志する時に、意志するところで、意志する人を愛し、 これらの権利を邪魔する者らを殺す権利を有する
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%9E#%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%9E%E7%9A%84%E8%AB%B8%E5%9B%A3%E4%BD%93
この言葉は主人公の行動規範にもぴったり当てはまるように思える。
主人公を含め、登場する殺し屋たちには名前がない、それぞれThe Killer、The Brute、The Expertと呼ばれるだけだ。それが抽象的な印象をもたらす。フィンチャー監督は勧善懲悪や復讐する男の物語が描きたかったわけではないのは間違いないだろう。有能な殺し屋である主人公は自分はその他大勢の一人に過ぎないとつぶやく。この映画は、強い者だけが生き残ると考え、他者に同情することのない資本主義社会で生きるリアリストたちは、殺し屋と変わらないのだと我々に語りかけているのだろうか?
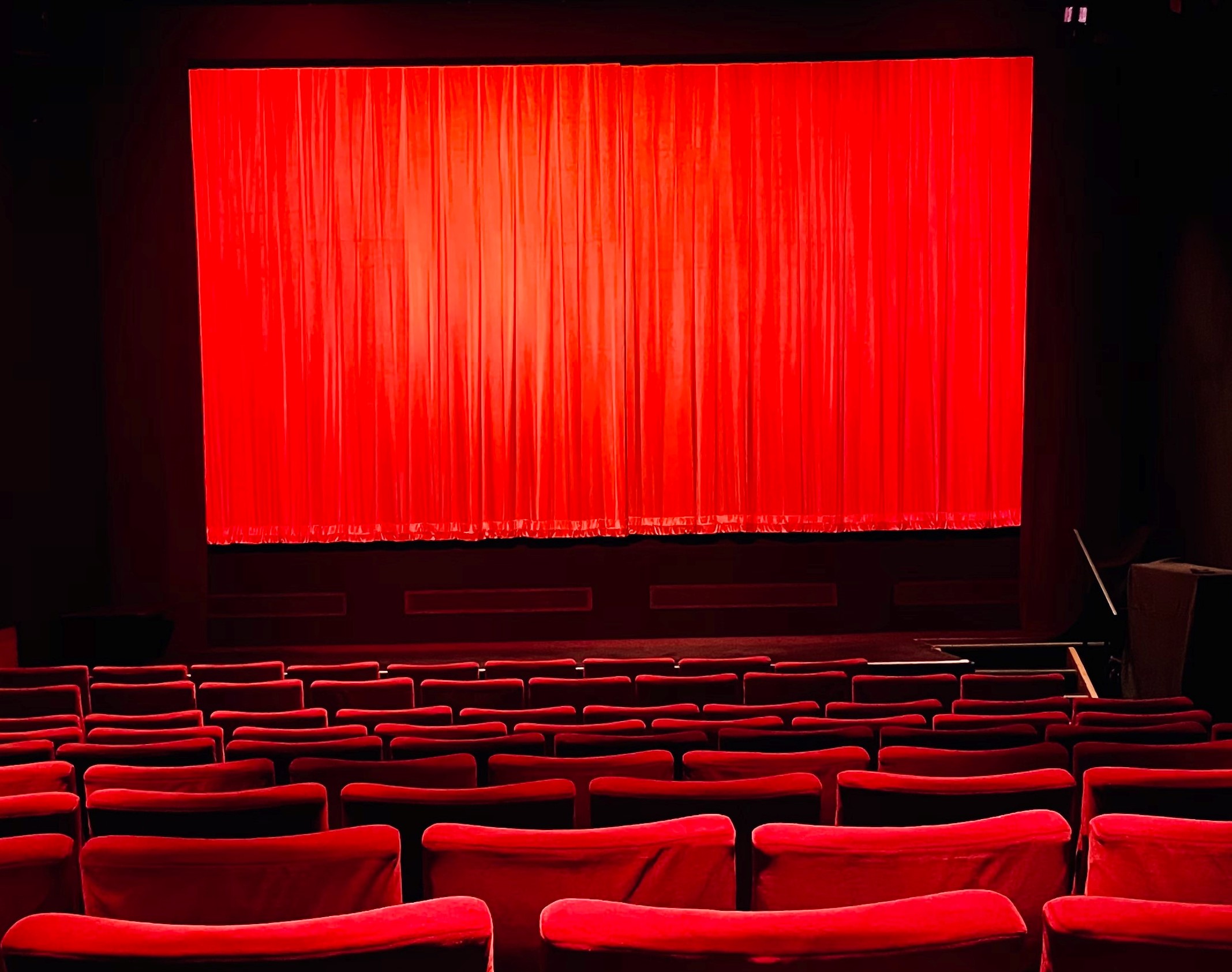


コメント