2005年から2009年にかけてボリビアのメノナイトコミュニティで実際に起きた事件から着想された小説の映画化。第95回アカデミー賞の脚色賞を受賞している。
実際に起こった事件というのは、眠っているあいだに家畜用の麻酔スプレーで昏睡状態にされ数百人もの女性たちがレイプされていた、というものだ。女性たちが受けた仕打ちは本当にひどくて、犯行自体は描写されないけど女性たちの肉体的精神的苦痛はしっかり描かれ、そのたびに心臓がえぐられる。映画はこの事件をドキュメンタリックに描くのではなく、女性たちの苦難の歴史、未来の希望を語る寓話として描く。
映画の冒頭で、”What follows is an act of an female imagination”、「以下は女性の想像力による行動」とキャプションが表示される。実際の事件ではこのような女性たちの投票や討議は行われなかったけど、あり得た、あるいは女性たちの胸の中に去来したであろう考えをドラマ化したという意味だろう。
映画の中の女性たちは完全に教育を禁止されていて文字の読み書きができないけど、メノナイトコミュニティでは女性も基礎教育は受けているらしい。読み書きができない女性たちは、さらに過去の女性たちや現代のタリバン政権下などイスラム原理主義の支配にある女性たちを連想させる。映画に登場する女性たちはただメノナイトという特殊な環境にいる女性たちだけでなく、過去や現在のあらゆる国の女性たちのことでもある。
事件が明らかになり犯人が逮捕され、女性たちがこれからどうするか、男たちを赦すか、男たちと戦うか、コミュニティを出ていくか、投票が行われる(この投票も原初的な民主主義の姿や女性の参政権の獲得を象徴している)。投票の結果、「戦う」と「出ていく」が同数になり、どちらを選ぶのか、コミュニティを代表する女性たちが議論することになる。
女性たちはみな世代や立場が異なり意見もバラバラだ。スカーフェイスと呼ばれる年配の女性(フランシス・マクドーマンド)は男たちを赦すべきと主張してそもそも議論に加わらない。彼女たちの信仰では、罪を赦さなければ天国に行けないのだ。女性たちの中でオーナ(ルーニー・マーラ)がいちばん理想主義的な意見を述べる。サロメは男たちを皆殺しにすべきだと激しい憎悪を滾らせる。子どもたちと共に夫から虐待を受けているマリシェは、男たちに意見することなんてできないと理想を説くオーナを批判する。男が女を支配するというシステムがこの犯罪を生んだのなら、男たちにすら罪はないのではないかという議論もされる。この状況を追認してきた母親世代から娘たちへの謝罪もある。ここで繰り広げられる議論は、いままで世界のいろんな場所で行われてきた議論をぎゅっと凝縮したものだ。
意見も対立する女性たちだけど、肉体的にも精神的にも深く傷つけられているという点は共通している。だからお互いの憤怒やとてつもない痛みには深い同情がある。彼女たちはお互いを支えあうように寄り添い、神に祈りを捧げ讃美歌を唄う。あらゆる権利や尊厳を奪われ命の危険にさらされている、そういう人たちを救うために生まれた宗教。その信仰を利用して権力を握っている男たちという皮肉。
男性だけが権力を握り女性から力を奪うコミュニティのシステムは、メノナイトの特殊なコミュニティだけのことではなく現代社会の似姿だ。システムを変えていく責任は男性にある。
議論の結果、女性たちが決断する選択には楽観的な未来は用意されていない。しかし、自分や娘たちに危害を加えるシステムの中に留まることはできない。そんなシステムや男たちを過去のものにして、未来に向かって進んでいくしかない。
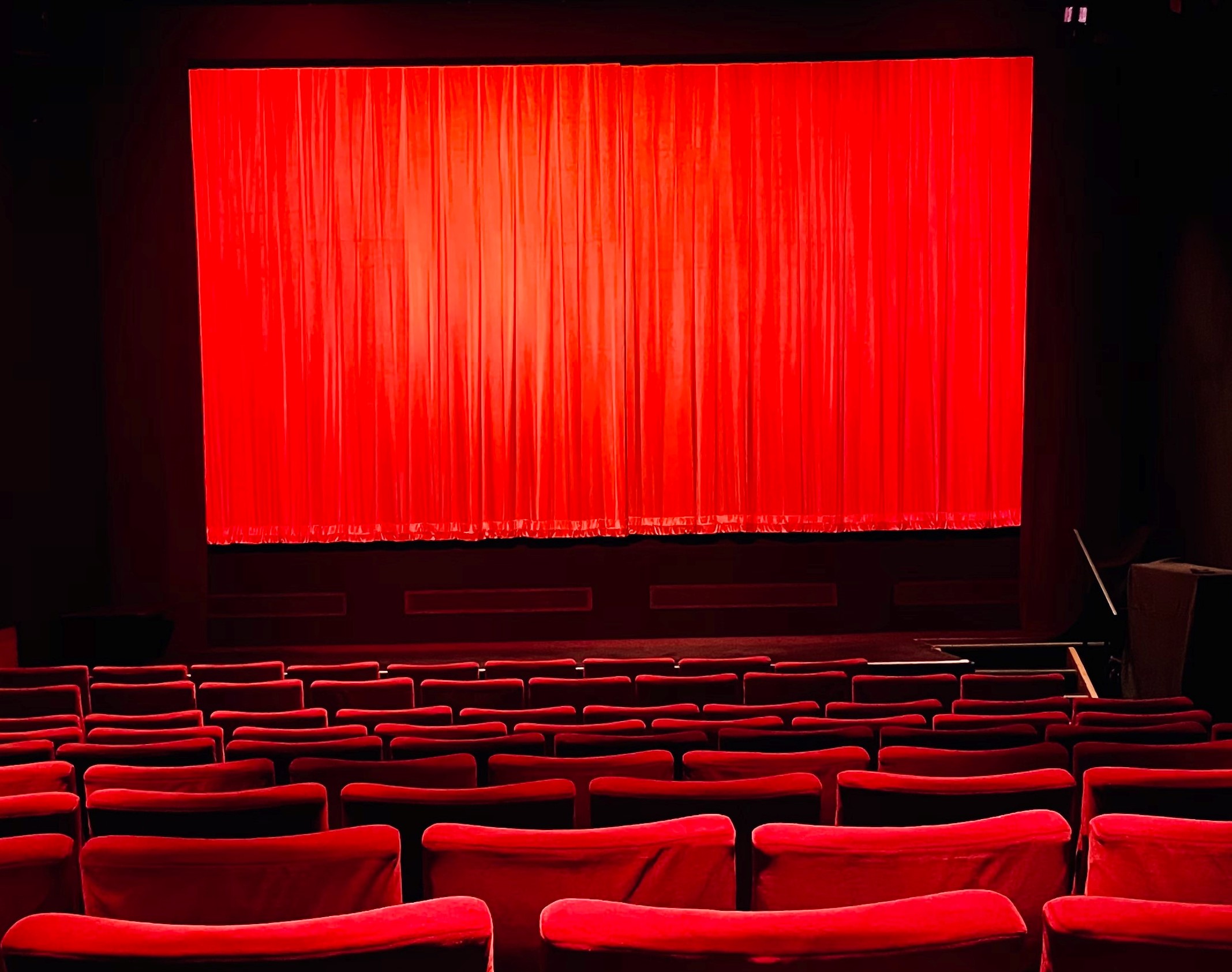


コメント