マテル社の人形おもちゃバービーを映画化。マーゴット・ロビーは主演とプロデュースを務め、監督と脚本にグレタ・ガーウィグとノバ・バームバックを指名したのもマーゴット・ロビーだったらしいというだけあって、バービー役がハマっている。
すべては「バービーとはなにか」という考察からできている
オープニングはいきなり『2001年宇宙の旅』のパロディから始まる。
バービーが革新的なおもちゃだったということと、赤ちゃん人形のおもちゃは女の子に性別役割を固定化させているというフェミニズムからの批判も重ねられたパロディだ。
次にバービーランドで目覚めるバービーのモーニング・ルーティーンが描かれる。このシーンは『レゴムービー』や『フリー・ガイ』とそっくりだ。3作ともおもちゃの映画化であり、メタフィクション要素があり一見ユートピアのような世界で暮らす主人公が、世界のおかしさやアイデンティティに悩むという展開も共通している。『レゴムービー』は『バービー』と同じワーナー・ブラザースの映画でもある。
この2作と『バービー』の違いは、『レゴムービー』『フリー・ガイ』ではアメコミやゲーム、ポップカルチャー、サブカルチャーがギャグのネタになっているのに対して、『バービー』はほとんどギャグが「バービーとはなにか」という考察から生まれていることだ。「バービーとはなにか」を考えることは、この社会で女性がどのように表象されてきたか、どのような女性像が理想とされているか、男女の権力関係について考えることにつながる。表面的にはバカバカしかったりシュールだったりする笑いの連続なのに、その背後には常に哲学的考察が貼りついている。『バービー』を観ていると、『レゴムービー』『フリー・ガイ』とは違って笑いだけじゃなく生真面目さと思弁的な感じを受けるのは、それが理由だ。
バービーランドから現実世界へ
バービーとは何かという考察がギャグになり、現実の問題にもつながるという構造は、映画全体の構造ともぴったり一致している。
バービーランドで幸せに暮らしていた主人公の典型的バービーは、ある日、死について考えてしまったりふとももにセルライトができてしまったり、人生が”完璧”でなくなっているのに気づく。それは現実世界に暮らすグロリアが、病んでたりキラキラしてないバービーを考えていたのが原因だった。
グロリアが勤めるマテル社は「女の子のため」という理念を掲げながら役員は全員男性で(現実のマテル社は半数近くが女性らしい)、グロリアはバービーが好きなのに商品開発には関われない。娘との関係もうまくいっておらず人生に屈託を感じている。
完璧さを取り戻そうとリアルワールドにやってきた主人公バービーとグロリアが出会い、お互いの人生が変化していく。
ナレーションの声はヘレン・ミレンで、「完璧なバービーの見た目じゃなくなっちゃった」と嘆くマーゴット・ロビーのセリフに対して「彼女が言うと説得力がない」とつっこんだり、メタ視点、神の視点の語り手だ。これは人形遊びをする子どもの視点を表しているのだ、と上記の記事では考察されている。これも「バービーとは何か」という考察が映画に反映されている一例だ。
バービーランドでは重要な仕事に就いているのは全員バービーで、ライアン・ゴズリング演じるケンは「俺の仕事は……ビーチだ」なんていってたりする。ケンたちの言動はとにかくばかばかしくて常に笑わせられるけど(弾き語りするゴズリングの声音とかいちいち最高)、これもケンという存在がバービーのキラキラした恋愛生活のためのアクセサリに過ぎないという洞察から来たものだ。ケンには職業も住む家の設定もないというのはドキッとさせられる。
また、リアルワールドにやってきたバービーが「私に性器はないの」というギャグシーンも、バービーとケンのアンバランスな関係が、人形遊びする女の子たちに対して性教育より前に恋愛しなければキラキラした人生は送れないという観念をすりこんでいるんじゃないかということを表している。
とにかくひたすらバービーとはどういうおもちゃなのかという考察が、この映画のギャグと構造を生み出している。
マテル社への批判的目線
ケンのアイデンティティクライシスや反乱をの描き方からもわかるように、この映画は(現実の)マテル社への批判も含まれている。
マテル社がモデル体型だけじゃないいろんな体型のバービーや、パイロットから大統領までさまざまな職業のバービーを発売しているのは、あらゆる女の子をインスパイアしエンパワメントしたいという理念を表していて、そのこと自体は否定してないんだけど、同時にそれが、キラキラとした「完璧な人生」の押しつけになっている。完璧じゃなくてもいいんじゃないか? というのがこの映画のメッセージは部分的にだけどマテル社への批判になっている。
商業主義や資本主義への批判もある。バービー人形はキラキラとしたイメージがあるからこそ女の子をひきつけることができて、それが商品力になる。だから劇中にでてきたような「鬱のバービー」は発売されない。映画の最後にグロリアは、キラキラしていない「普通のバービー」を提案する。「それは最悪のアイデアだな」と否定するマテル社CEO(ウィル・フェレル)だが、マーケット担当から「売れますよ」といわれて即座に「最高のアイデアだ」と意見を翻す。このシーンも、笑いと同時に完璧な人生の圧力と商業主義への批判にもなっている。
人は完璧を目指さなくてもいい、でも映画は完璧を目指さなくてはいけない。
劇中で、主人公バービーが「よっ、白人の救世主!」とツッコまれる場面があって、この映画はこのようなつっこまれる隙をあらかじめぜんぶギャグにして潰してある。そうしておかないと、主人公バービーがグロリアの娘に辛らつな言葉で叩き潰されたように、SNS上で叩かれ駄作の烙印を押されることになってしまう。そうなったら興行成績は絶望的だ。いまだに大作映画が女性監督に任されることは少ない。ガーウィグ監督の肩には、200億円近い製作費だけでなく、女性監督の未来も重荷となってのしかかる。だから失敗するわけにはいかない。あらかじめあらゆる隙を潰しておかなければならない。女も男も完璧じゃなくてもいいじゃないかというのがこの映画のメッセージの一つだけど、映画自体は完璧を目指さなくてはいけなかった。
おそらくマテル社が当初期待していた映画というのは、バービーランドだけを舞台にした、ちょっと風刺を効かせたシュールな笑い満載のコメディ映画に多様な女性を象徴するバービーって素晴らしいというメッセージをのせたような映画だったのかもしれない。それはそれでひとつの映画として十分成立しただろう。しかしプロデューサーであるマーゴット・ロビーとガーウィグ監督はそこで留まることをせず、さらに先を、完璧を目指した。
この映画は、バービーをフェミニズムの敵と批判する映画じゃないし、バービーは多様な女性をエンパワメントしてて素晴らしいってだけの映画でもない。男女を逆転させた風刺に終わる映画でもないし、やっぱり男がいなくちゃって映画でももちろんない。それらすべてを笑いにしながら一つずつ積み上げていき、さらにその先に行こうとする映画だ。
そして、少なくとも興行収入的にはそれは成功したといえるだろう。
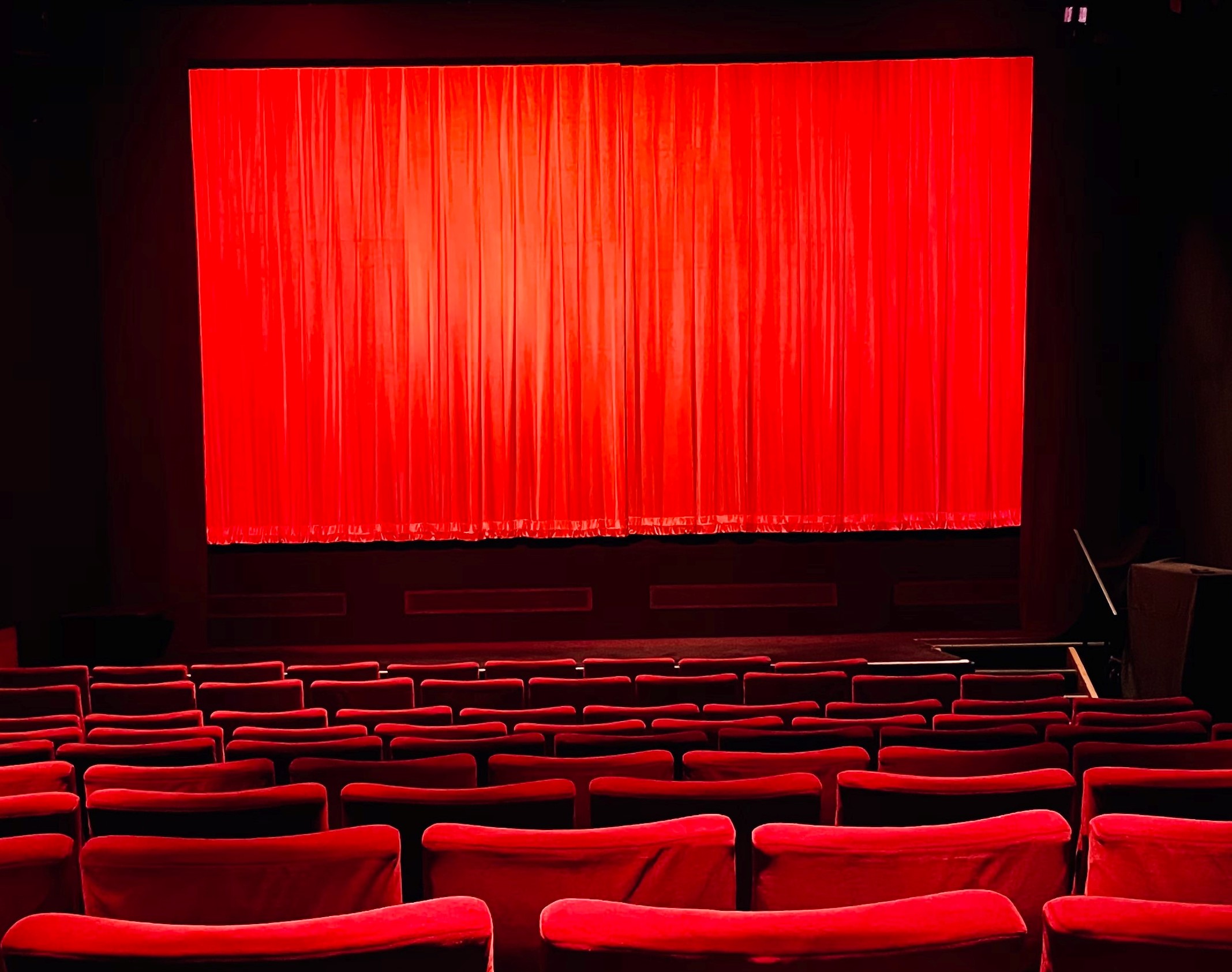



コメント