まずめちゃくちゃおもしろかったし世界観を楽しめた。その一方で、「これで終わりなんだ」と強く思わされて、悲しくて涙が出てしかたなかった。
今作はいままでの宮﨑駿監督作とは大きく違った作品だと思う。
『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』や『ハウルの動く城』とも違うごりごりのファンタジー
そう感じる1つめの理由。いままでの作品でも、現実の世界とは別の理に支配された世界が構築されていたけど、今作に特に強くごりごりとしたファンタジー性を感じた。これまでの作品は、主人公たちに焦点があたり彼ら彼女たちを引っ張っていく強いストーリー性があった。それに比べると今作は、「下の世界」にいる眞人はほとんど傍観者で、とくに後半になるにつれて物語の論理は破綻し崩壊していく。そのおかげで、隠されてる神秘的なものへの驚異、世界の不思議さ、畏怖だけが強く観客の印象に残るようになっている。それが強いファンタジー性を感じさせる理由じゃないだろうか。
主人公の違い
たとえば『カリオストロの城』での屋根から屋根への大ジャンプシーン、『天空の城ラピュタ』でパズーがラピュタの外壁にしがみつき登っていくシーン、『未来少年コナン』でラナを抱えての落下と着地シーンなどなど、誇張されてるけどリアルで絶妙なバランスで視覚的快楽を与えてくれるアクションシーンが今作にはほとんどない。やはり年齢的に原画能力が衰えたせいだろうかと思ったんだけど、次の記事を読んで理由が腑に落ちた。
「陽気で明るくて前向きな少年像(の作品)は何本か作りましたけど、本当は違うんじゃないか。自分自身が実にうじうじとしていた人間だったから、少年っていうのは、もっと生臭い、いろんなものが渦巻いているのではないかという思いがずっとあった」
https://book.asahi.com/article/14953353
アクションシーンがないのは、今作がパズーやコナンとは違う、うじうじとした少年を主人公として描かれているからなのだ。それは自ずから作品内容の性質も変えることになる。少年少女をはらはらどきどきさせ最後には笑わせるような過去作とは違ったものにならざるをえない。これがいままでの作品との違いを感じさせる2つ目の理由だ。
いままでの作品の引用でできたモザイク
3つ目の理由は、自作からの引用が大量にあること。前述のアクションシーンや飛行シーンなど、どの宮﨑作品にも共通して刻印されているトレードマークのようなものはあるけど、今作ではそうじゃない直接的な引用が多かったように思う。たとえば、病気の母、母親を喪う恐怖というのは『トトロ』だし、自伝的要素、太平洋戦争の描写は『風立ちぬ』だし、「下の世界」で列をなして進んでいく船たちは『風立ちぬ』で列をなして飛ぶ死んだ飛行機乗りたちの魂を連想させるし、少年主人公の冒険活劇、廃墟になった王国、ラストの崩壊は『ラピュタ』だし、瀕死で血を流すペリカンは『もののけ姫』の乙事主そっくりだし、魔法の世界とそこからの現実世界への帰還は『千と千尋』だし、奉公人の老女たちとその中の1人だけが気難しくて辛辣なことを言うのは『崖の上のポニョ』の「ひまわりの家」にいる老女たちそのままだし、老女が若くなって躍動するのは『ハウル』だし、映画の冒頭、夢の中の火事のシーン『火垂るの墓』(これは高畑勲監督作だけど)を連想させる……。これ以外にも気づいてないところもあるはずで数え上げて行ったらきりがない。
いままで作品を作るたびに監督が苦心惨憺七転八倒していたのは、「いままでと同じことをしていては仕方がない」という思いからじゃなかっただろうか。それなのに今作では過去作からの直接的な引用が大量にある。
これらの引用を観せられているうちに、ああ、これが宮﨑駿がわれわれに残してくれたもの、餞別、別れの挨拶なんだろうかと思ってしまって涙が止まらなくなってしまったのだ。鈴木敏夫プロデューサーが宣伝なしで行こうと思ったのは、「戦時中を舞台にした作品」とか「不思議な世界に迷いこむファンタジー」だとか観客に予断を持たせないためや純粋なビジネス的判断かもしれないけど、あるいはプロデューサーが作品を観て、墓標を前にしたような厳粛な気持ちになったからかもしれない、とさえ思った(どちらにしても最高の選択だった)。
「海の世界」=ジブリ
そんな過去作からの引用でいっぱいの「海の世界」を創り出したのは、行方不明になっていた大叔父だった。ファンタジー世界を創ったクリエイターということで、どうしても宮﨑駿、あるいはいっしょにジブリを立ち上げた高畑勲を重ね合わせてしまう。しかしそんな「海の世界」はペリカンにいわせれば地獄のような世界で、インコたちは人間を食い殺している(食べられてしまったらしい鍛冶屋がどういう存在なのか気になってしまう)。これから「上の世界」に産まれでようとするワラワラたちは、アニメートされた命そのものであり、アニメ作品を表しているのだろうか。ワラワラたちがペリカンに食べられたりヒミの炎で焼かれたりするのをみて、監督が過去に日本のアニメーションの現状について言っていたことを思い出してしまう。しかも、その「海の世界(=ジブリ)」は最後に大叔父(=宮﨑駿)とともに崩壊してしまうのだ。それもこの映画から強く訣別を感じた理由だろう。
これが最後の作品になる?
宮崎駿監督としては、自分は引退中であり引退しながら作っているという認識らしい。だからジブリ美術館用の短編とか小品が作られる可能性はあると思うけど、しかし今作以前のような長編作品が作られることはないんじゃないだろうか。なぜなら、これまで書いてきたように今作はいままでの作品とは様々な点で違っている特異な作品で、これはジブリやアニメーション作家である宮﨑駿に対する訣別、死を表明した作品だと思われるからだ。
大童氏はこう言うけど、もし次の長編作品があればそれが原初の宮崎作品になるかもしれない。でも再び生まれるためには死ななければならない。もし新しい作品が作られたとしても、今作が「死」であることにはかわりない。今作が作家宮﨑駿への別れの作品となるのか、生まれ変わった宮崎駿がみられるのか、それはまだわからない。
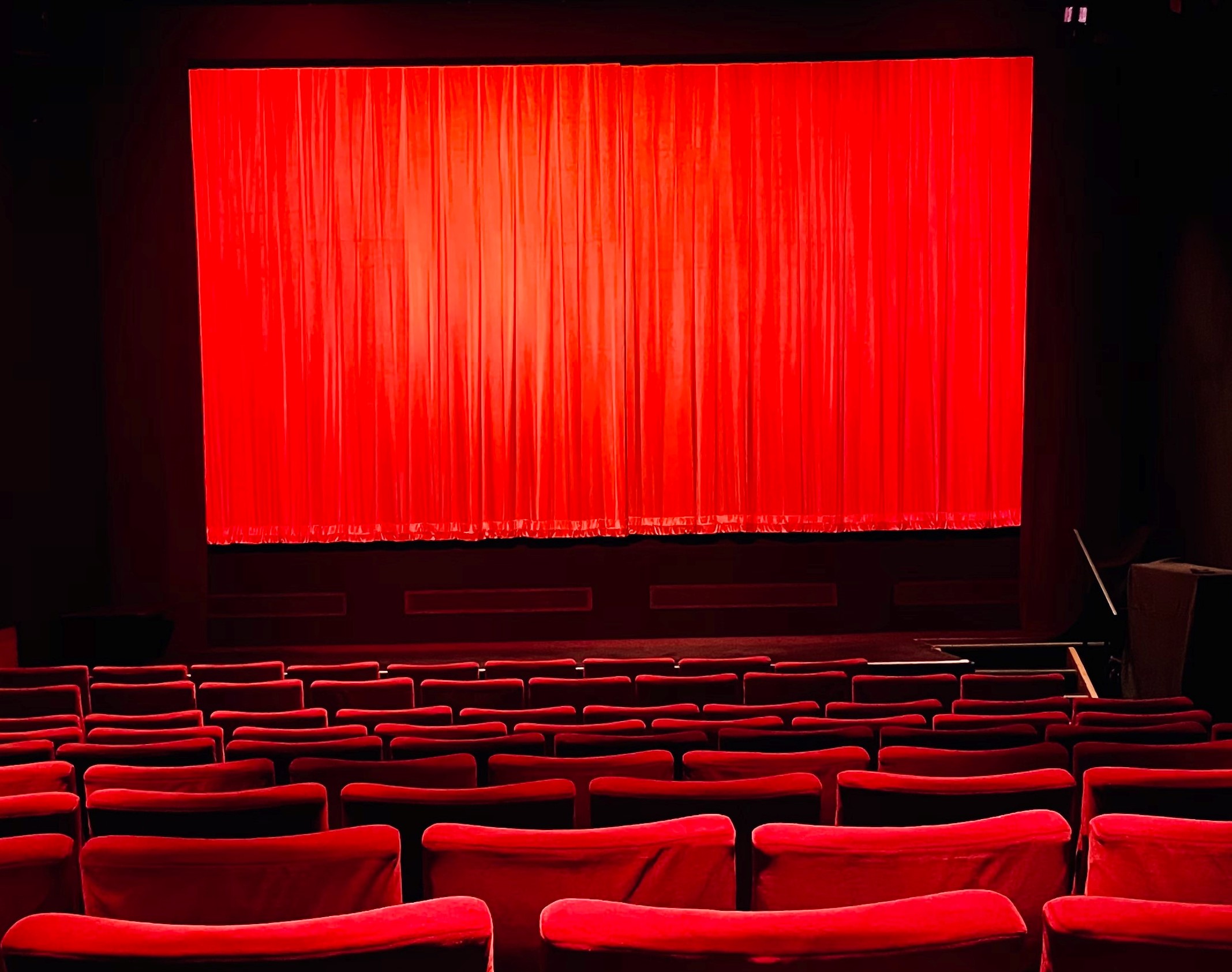


コメント