映画は夜景から始まる。家々やビルの明かりが湖を囲むように輝いている。真ん中にある湖は真っ黒で、町の中心に空いた巨大な穴のように見える。
ガールズバーへの放火事件や学校での体罰問題などいくつかの事件がシングルマザーである早織、息子の湊、湊の担任である保利の3人の視点から描かれる。
シングルマザーとして湊を育てる早織は息子の様子がおかしいのに気づき、学校で何か問題が起こっているんじゃないかと疑う。息子から担任から体罰や暴言を受けたと言われた早織は学校に乗りこむ。対応した校長や担任の態度はひどいもので、回答は政治家か官僚の答弁そのままだし、担任の保利の謝罪はしどろもどろだし、早織が激怒するのも当然だ。しかし学校側の対応は”モンスター”ペアレントへのマニュアル的な対応に終始する。早織からすれば学校と担任教師の保利こそが「怪物」だ。
視点が担任教師である保利に移ると、早織の視点からだととんでもない教師にしか思えなかった保利だけど、ちゃんと受け持ちの子どもたちのことを考え、生徒たちからも慕われていて、謝罪の時の言動にも理由があったことがわかる。ただ、生徒への言動が無神経だったり、恋人にエレベーターの中でプロポーズしたり、人の気持ちがわからないところがあるというのもわかってくる。
湊が訴えていたことは事実ではなかった。保利からすれば湊は嘘をついて自分を陥れ、その結果仕事も恋人も失うことになった。保利からすれば学校を守るために自分をスケープゴートにした校長と学校組織、そして湊こそが「怪物」だ。無責任に噂を流す親や同僚教師たち、週刊誌の煽情的な報道、バラエティ番組の影響など、観客の頭の中にも「怪物」が現れては消えていく。
真実は何なのかどんどんわからなくなってくるけど、ひとつはっきりしているのは、新しい視点が導入されるたびに地獄としか感じられなかった状況に少しずつ光がさしていくように感じられること。早織が学校と問題教師を「怪物」とすることで地獄が現出する。保利にとっては湊や学校、マスコミが「怪物」で、そのような認識でいる限り地獄のような状況に囚われ続ける。でも真実は早織や保利の認識からちょっとだけずれたところにある。そのことが明かされるにつれて「怪物」といっしょに閉じこめられた密室にブスブスと穴が開いていく。
早織や保利は一方的な被害者でないこともわかってくる。早織は湊に対する「そんなことしてたら女の子にモテないよ」とか「普通の家族を持ってほしい」というちょっとした言葉が抑圧になっていることに気づかない。保利は生徒たちを思いやっているつもりでもクラスでのいじめには気付かないし、生徒への言動が無神経だったり、依里がサイズのあわない靴を履いていることやあざに気づいても虐待には思いが至らない。2人とも、偏見や思いこみに囚われているせいで子どもたちに助けが必要なことに気づけずにいる。
少しおとなびていていろんなことを知ってるけど言動がちょっと変わっていて、そのせいで同級生からいじめられている変わり者の依里。自分も「人とは違う」と自覚する湊はそんな依里に好感をもち、2人は親しくなっていく。トンネルの先にある秘密基地は、大人たちには見えない/見ようとしない領域の象徴だ。2人はそこで遊び成長していく。湊は依里を拒絶してしまったりして関係が壊れそうになるが、ちゃんと謝罪して仲直りする。なにかのきっかけで二人の仲を知った父親は無理やり仲を引き裂こうとする。いったんは「好きな女の子ができた」と嘘を言わされた依里だったが、父親の制止を振り切ってそれは嘘だと湊に告げる。2人は大人たちの助けを借りず自分たちだけで困難を乗り越えていく。映画のラスト、家出した彼らを早織と保利が探しに来るが、2人のもとには帰らない。
「怪物」は偏見や憶測、予断から生まれ、それを生み出した人を地獄のような状況に閉じこめてしまう。「怪物」は幻想だけど、すべては見方によると相対化してしまえばいいわけではない。クラスのいじめや虐待、無責任な噂を流す悪意など、残酷な現実はまぎれもなく存在している。しかしこの物語を悲劇で終わらせるわけにはいかない。映画のラストで2人は楽しそうに雨上がりの光が指すほうへ向かっていく。彼らが向かっていくのは、大人たちが用意しなければならない明るい未来だ。
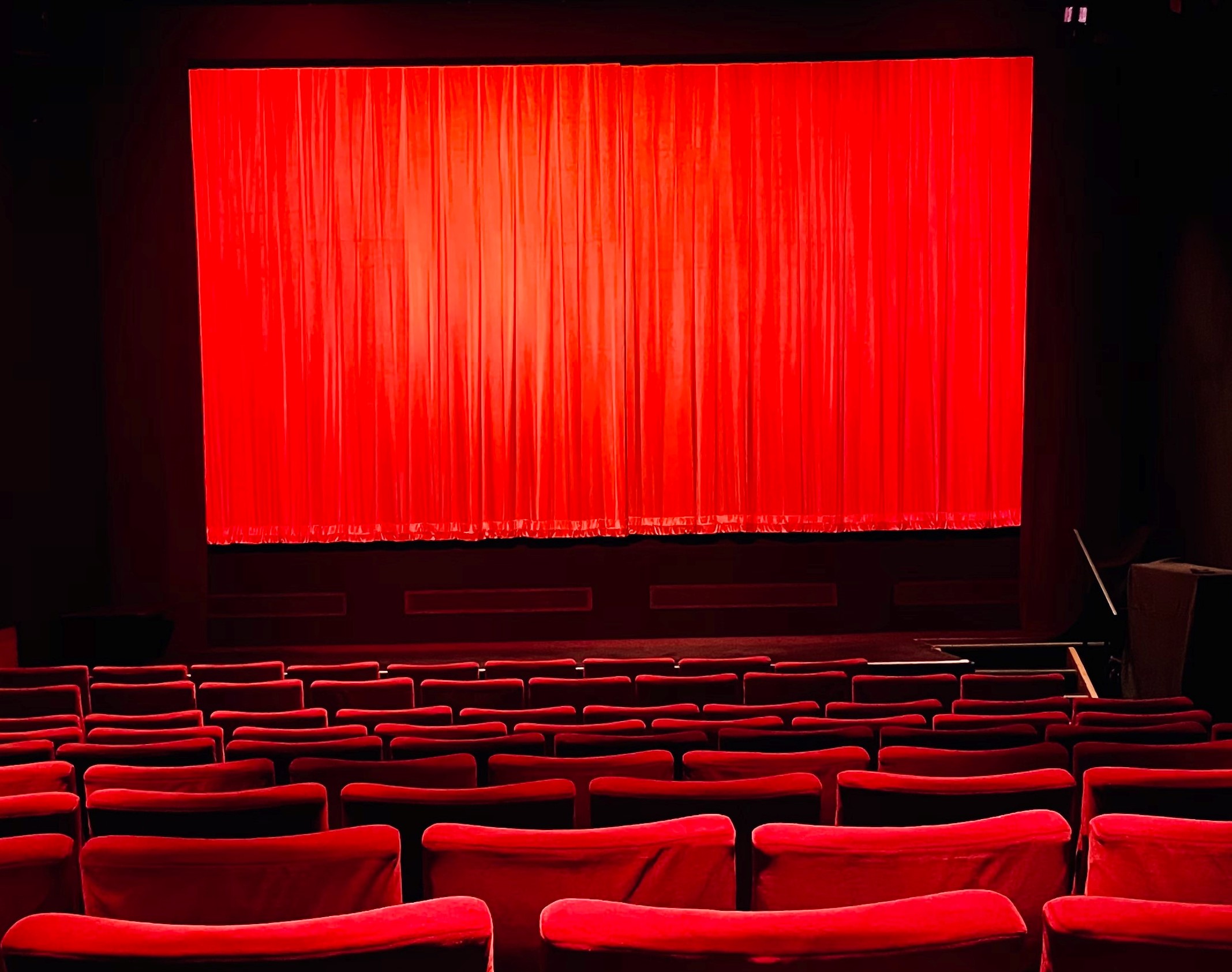


コメント