結論からいうと、イギリスの科学社会学者である著者は「我々みんなが科学の専門家ではない」と考えている。1960年代あたりから科学的なことも科学者だけに任せておけないという流れがおこった。しかし専門の領域から離れれば離れるほど議論は極端になってしまう。科学者以外の市民も科学者と対等に科学的な議論をすべきだ、ということになるのは危険だと著者は訴える。
戦後から現在までの科学に対する「時代精神」の変化、科学論史をたどりながら、専門家の専門知とはどういうものなのか、なぜ素人は専門家と議論できないのかを論じていく。
科学論の第3の波
科学論の第1の波では、第二次大戦での科学技術の貢献の影響もあり、科学の輝かしい英雄的な側面が論じられていた。
しかし1960年代になるとあらゆる権威が疑われるようになり、科学の営みというのは英雄的な科学者だけのものではなく、混沌に満ちたプロセスであることがわかってくる。科学論の第2の波では科学の失敗や混乱を論じるようになる。
それに加え公害、薬害、経済予測の失敗、原発事故などが起き、人々の科学に対するイメージはどんどん悪くなる。科学の権威は地に堕ちていき、科学的な問題を科学者だけに任せていていいのだろうか、自分たちの生活にかかわる問題は科学者なんかより自分たちのほうがわかっているんじゃないかと考える人たちが出てくる。
著者は「我々みんなが科学的議論をするべきだ」とは考えない。なぜならわれわれは科学の専門家――科学者ではないから。もちろん配管工は配管の専門家だしプログラマーはプログラミングの専門家で、酪農家は牛や羊の専門家だ。しかし科学の専門家ではない。新型コロナワクチンに効果があるのか、どのような副作用があるかというような議論はできない。門外漢の素人が何年もの経験と学習を重ねて科学者と議論できるような専門家になることはある。とはいえ、本を何冊か読んだり論文を何本か読んだりしただけでは科学の専門家にはなれない。科学的議論は科学の”徒弟制度”を経た科学者同士でないとできないのだ。民主主義の理想としては、すべての市民が科学者になり科学的議論ができるのが理想だけど、そんなことは不可能だ。科学的議論は科学者と科学コミュニティに任せるしかない。
しかもそのプロセスは時間がかかる。可能性は少ないだろうけど、もし多数派の科学者が信じている学説が間違っていたとしても、それが判明するのは何年も何十年も先のことになってしまう。
では、科学者でない人たちはそれまで黙って待っていなければいけないのかというと、そうではない。陰謀のようなものがあるならその証拠を見つけることが必要だ。ジャーナリストは科学者が大企業から資金の提供を受けてその企業に有利な研究をしていないかとか、政治的イデオロギーや偏見に囚われていないかを調べたりすることができる。マスコミやネット上でするべきなのは少数派の論文を紹介したり、多数派の学説が正しいかどうかという科学コミュニティ内部で行われるような議論ではなく、(もし存在するなら)科学の外側にある不正の証拠を見つけ出すことだ。
理想的な科学者と科学コミュニティには公平無私とか知識の共有とか普遍主義(反差別)という”徳性”がある。その徳性ある科学者たちを著者は聖職者に例える。もちろん堕落した聖職者がいるように不正をする研究者や志の低い研究者もいる。しかしそういう研究者は科学コミュニティ内からも尊敬されないし、ジャーナリストが証拠を見つけて指弾することも可能だ。
われわれみんなが対等に科学者と議論できるのだと考える人たちが多いから、ワクチン陰謀論や人類が原因の温暖化否定論や放射能デマが蔓延ってしまう。そういった流れを押し戻して、科学のプロセスのリアルさを見つめながらも、”徳性”のある科学を特別なものとして語ろうというのが著者の提唱する科学論の第3の波らしい。
しかし、科学へのリスペクトを取り戻すにはどうしたらいいんだろうか? 影響が大きいテレビや新聞、教育、ソーシャルメディアのありかたを変えないといけないんだろうけど、一朝一夕に変えるのは難しいだろうな。
しかし、縁起でもないけど、次のメルトダウンやパンデミックや大地震が起きる前に状況を改善しなければ、またデマの蔓延を繰り返すことになる。
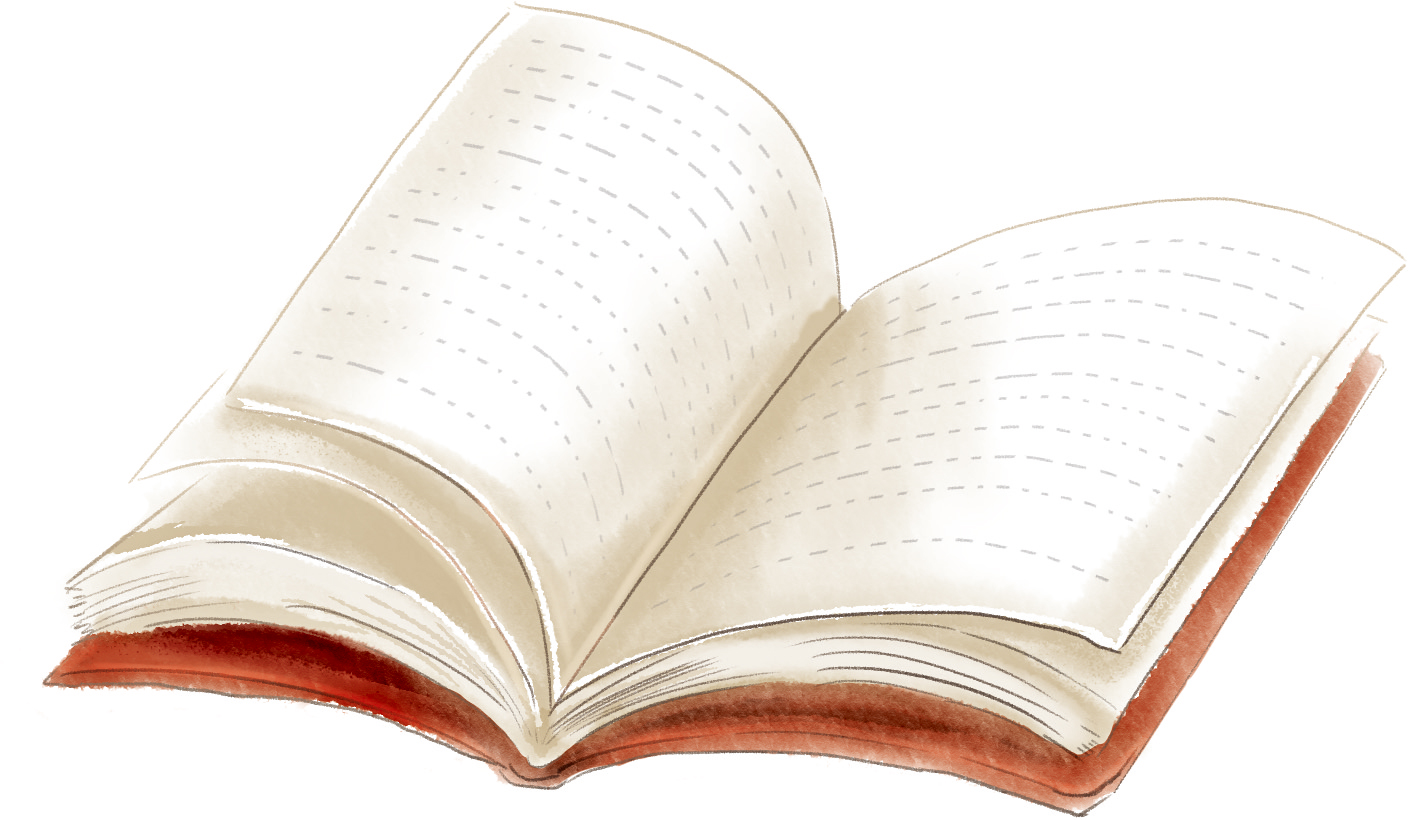


コメント