元バレリーナであり研究者としての経歴もある科学ジャーナリストでありマゾヒストを自認する著者による、痛みの生理学から主観的な痛みの現象学まで、苦痛について考察した本。
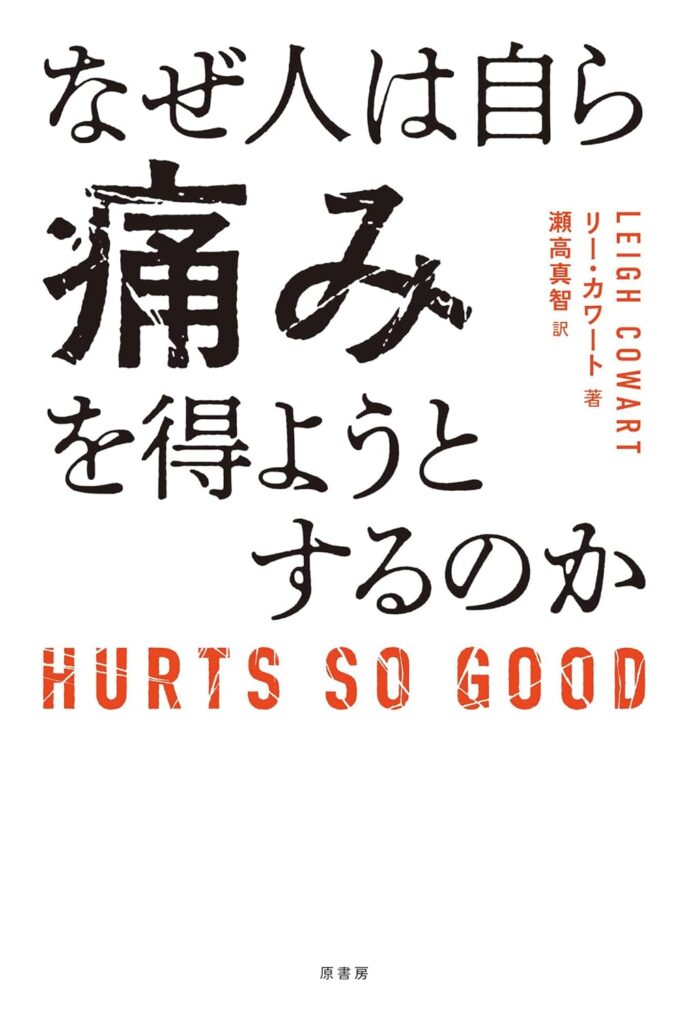
いきなり著者であるリー・カワート自身の濃厚なSMプレイの描写から始まるのでびっくりするけど、彼女が指摘するように、性的なマゾヒズムだけでなく、たしかに自ら進んで苦痛を求めているとしか思えない行為は意外に多い。最近流行っているサウナで”ととのう”のもそうだろうし、丸2日以上も不眠不休で走り続けるウルトラマラソンや、超激辛のトウガラシの大食い大会、世界中の苦行者たち。自分の体に直接ワイヤーをつなぎ巨大な風船に吊り下げられるパフォーマンスや、鼻に釘を打ちこむ芸人、ウルトラマラソンやトウガラシ大食い大会を喜んで観に来る人たち。参加者はもちろんだが、観客はなにを期待してくるのだろうか。参加者の苦痛に対してサディスティックな喜びを感じているとは思えない。苦しむ参加者を観て間接的に自分も苦痛を感じることを求めているのではないだろうか。
しかしなぜわざわざ苦しく痛い思いをしなければならないのか。著者はそれにはさまざまな理由があると考えていて、1つの答えを用意してはいない。
答えの1つは、痛みを感じるとエンドルフィンが出るということ。エンドルフィン(endorphin)とは、内因性の(endogenous)+モルヒネ(morphine)という意味で、つまり痛みを感じれば脳内麻薬が出て快感を得ることができるのだ。
もう1つは、宗教的苦行者のように自分を罰することで神となんらかの取引をしようとすること。中世ヨーロッパでペストが流行したとき、神の赦しを得ようと自分を鞭打ちながら巡礼した人たちがいた。苦行者はキリスト教だけでなく世界中の宗教に存在する。
1つは、極端でタブーな行為が人に特別な行為をしているという感覚を与えてくれるということ。特別ですばらしい達成というのは、たいてい苦痛が伴う。だから苦しくつらい思いをすると自分が特別であるという錯覚が生まれるのだろう。著者は自身の拒食症体験を語る。空腹であることや暴飲暴食をしてすぐにすべて吐き戻したりすることはとても辛いし命の危険もあるが、達成感や心の平穏ももたらしてくれる。
もう1つは、自傷行為のように肉体的苦痛によって精神的苦痛をまぎらわしたり、自分が肉体や苦痛をコントロールできるという感覚を得るためということも考えられる。もし手のひらに釘を打ちこんだら、その瞬間そのこと以外のことを考えることはできなくなるだろう。
痛みによって、快感や心の平穏、自分は正しいという感覚、悟りに近づくような「今ここ」の感覚や贖罪が得られる。しかし、著者は痛みを手放しで肯定しているわけではない。自分でコントロールできない苦痛は虐待になるし、過激なSMプレイや自傷行為は命にかかわることもある。有害な自傷行為とそうでない自傷行為の境界はグレーゾーンになっていて、自分自身過激なSM行為をすることもある著者は、そのグレーゾーンの境界や自分自身の性癖の謎を見極めようとこの本を書いたのだ。
著者はバレリーナ時代の過酷な練習生活についても語る。爪先で立ち続けていると足の爪がはがれ、足先は血まみれの肉塊のようになってしまう。虐待的な指導者もいるし練習中に失神する生徒もいる。それでも著者にとってバレリーナ時代は甘美な思い出でもある。バレエの道を諦めたあと、もう苦しい練習をしなくてもよくなったのに著者は空っぽになったように感じる。かつてバレリーナ仲間だった女性にも取材をしていて、彼女はいまはキックボクシングをしている。キックボクシングの練習も試合もやはり肉体的精神的に苦痛にあふれている。
格闘技や過激で危険な行為をする『ジャッカス』は、最近読んだ『人はなぜ格闘に魅せられるのか』では「男らしさ」やテストステロン、進化学で説明されるが、本書ではマゾヒズムという観点から掘り下げられていたのが興味深かった。
「なぜアクション映画の主人公は血みどろになり観客はそれを楽しむのか」というのが個人的興味でこの本を手に取ったんだけど、著者の考察は刺激的で参考になるものばかりだった。
この本を読む前は、アクションシーンやバイオレンスは観客の脳内にアドレナリンを出させるためのものとしか思えなかったけど、読んだ後は、アクション映画の主人公は積極的に痛みを求めているというように見えてくる。
フィリップ・マーロウはきまって警官や悪者にぼこぼこにされ、ダシール・ハメットが原作の『用心棒』では三十郎が足腰が立たないくらいぼこぼこにされる。
ポール・シュレイダーはトラウマや罪悪感から自分を傷つける主人公の映画を延々と作り続けている。
シュレイダー監督の『魂のゆくえ』
『ビューティフル・デイ』の主人公はハンマーで敵を殴りまくるけど、過去のトラウマから自殺未遂を繰り返す。『ザ・コンサルタント』の主人公は自閉症で自分を痛めつけることを日課にしている。
『ジョン・ウィック』で自ら指を切断するシーン
この本の著者であるリーは元バレリーナで過酷な練習に耐えていたけど、『ジョン・ウィック』にもバレエが出てくるし、新作スピンオフのタイトルは『バレリーナ』らしい。
評価されるアクション映画って一方的に敵をぶちのめすんじゃなく、主人公側もぼろぼろになる。観客は登場人物が感じる苦痛を、自分も間接的に感じることを求めてるんじゃないだろうか。
次はこの本の参考文献にあった『痛みの文化史』を読んでみようと思うけど、誰か「痛みと苦しみの映画史」みたいな本書いてないんだろうか?
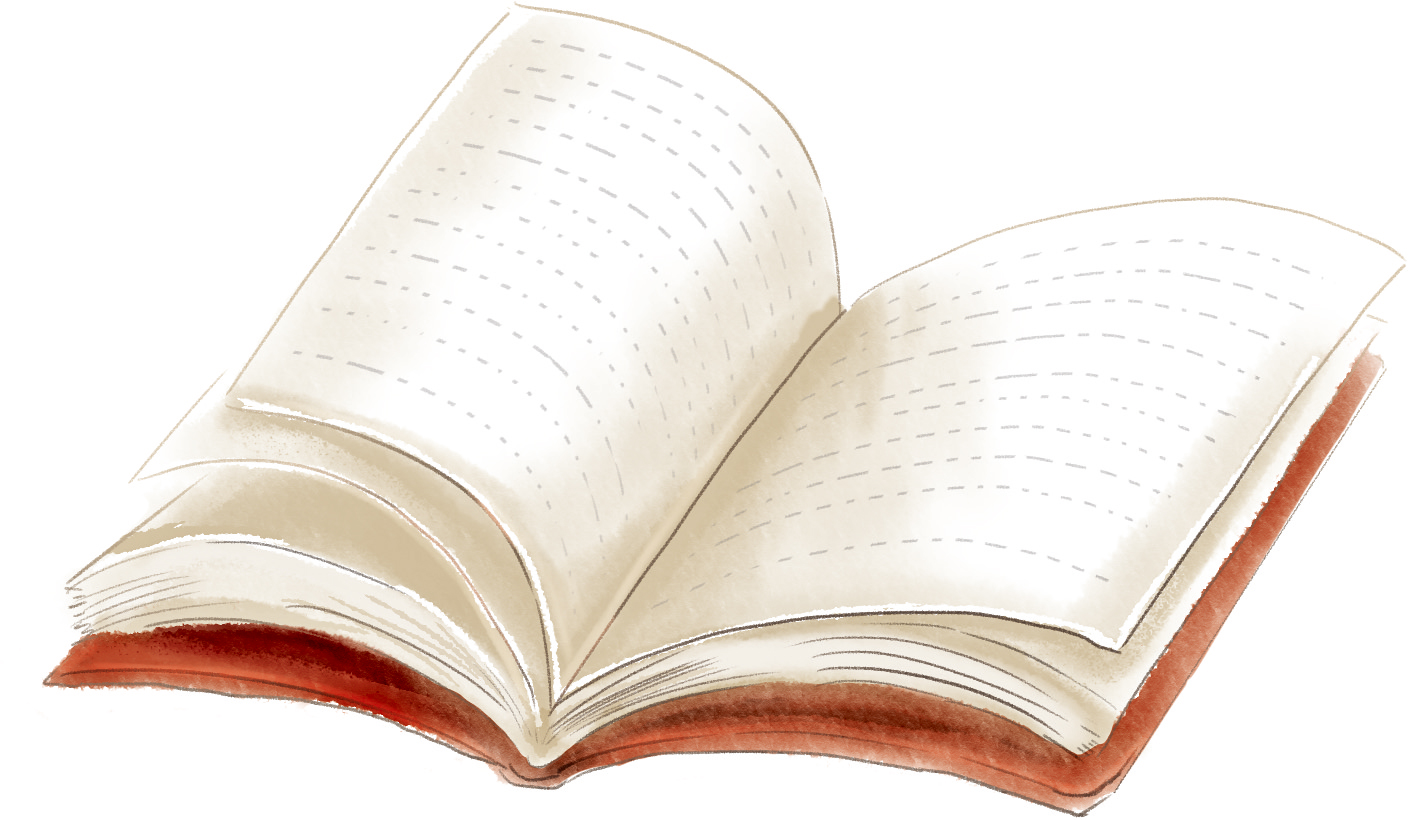


コメント