前作『ジョーカー』でアーサーは、病気に苦しみながら生きる自分を冷酷に扱う社会や人々への怒りを爆発させ、ジョーカーとなって5人の人間を殺害し、アーサーとしての人生では味わえなかった最高の気分を味わう。しかし、怒りは正当なものであっても5人もの人間を殺したことは身勝手な行為というしかない。しかもジョーカー信奉者を生み出して社会に混乱をもたらすことになった。
前作が公開された1年3か月後、議会議事堂襲撃事件が起きている。直接『ジョーカー』が影響したとは思えないが、襲撃犯たちの姿はトッド・フィリップス監督に現実にも発生したジョーカー信奉者たちの姿を思い起こさせたのではないだろうか。だから続編である『フォリ・ア・ドゥ』では、ジョーカーという妄想を徹底的に叩き潰すことにしたのだろう。
映画冒頭のアニメーションでは、ジョーカーのやったことの”濡れ衣”をアーサーが着せられてしまう。ジョーカーを叩き潰すということはアーサーを叩き潰すということになってしまうのだ。幼少期から虐待され、大人になってからも社会から痛めつけられていたアーサーは、続編でさらに徹底的に痛めつけられることになる。しかも、もうジョーカーという妄想に逃げこむこともできない。
アーサーとジョーカー、どちらに責任があるのだろうか。アーサーかジョーカーか、正気か狂気かという綱引きを本作は法廷劇として、ミュージカルとして描いていく。
アーサーかジョーカーかというテーマは2つの曲にも表れている。
映画の最初のほうで出てくる曲”What The World Needs Now Is Love”にはこんな歌詞がある。
Lord, we don’t need another mountain
There are mountains and hillsides enough to climb
主よ、もう山は必要ありません
登らないといけない山や丘はもうたくさんです
もう1つ、リー(レディ・ガガ)が歌う”Gonna Build a Mountain”はこんな歌詞だ。
Gonna build me a mountain
From a little hill
Gonna build me a daydream
From a little hope
Gonna push that daydream
Up the mountain slope
Gonna build a heaven
From a little hell
私に山を築かせる
小さな丘から
私に白昼夢を築かせる
小さな希望から
その白昼夢を山の斜面に押し上げて
天国を築かせる
小さな地獄から
「丘も山もいらない」という歌はジョーカーよりもアーサー、狂気よりも正気を求めることを意味し、リーは逆に「小さな丘から山を築く」「小さな地獄から天国を築く」と歌い、アーサーにジョーカーでいることを求める。2つの曲が対立するように、アーサーは自身でいることとジョーカーになることの間で引き裂かれる。
自尊心を満たすため、あるいは恋愛妄想としてアーサーはジョーカーに引き寄せられる。しかし、そのたびに手ひどく痛めつけられる。
前作でアーサーと同じアパートに住んでいたソフィー(ザジー・ビーツ)も法廷の証言に立つ。ソフィーは前作の事件後に作られた再現ドラマでの描かれ方のせいでジョーカー信奉者にいやがらせをされたという。再現ドラマの内容はわからないが、アーサーに同情的な内容だったため、アーサーを拒絶した(拒絶するのが当然だが)ソフィーがバッシングされることになったのかもしれない。アーサーに同情し擁護することはジョーカーも肯定することになってしまう、だからアーサーも徹底的に痛めつけられなければならないということだろうか。
『タクシードライバー』の脚本で有名なポール・シュレイダーは中年男性がひたすら苦しむ映画を撮り続けている。2018年アメリカ公開の『魂のゆくえ』でも、主人公の牧師は末期がんの治療を拒否し、教会の方針に疑問を覚えいままで信じてきたことは正しかったのかと精神的に苦しみ、映画のラストでは自分の体に鉄条網をまきつけ血まみれになる。それでもラストには慰め(主人公の妄想かもしれないが)が用意されている。
『魂のゆくえ』などのシュレイダー監督の作品、ホアキン・フェニックス主演の『ビューティフル・デイ』、『ジョン・ウィック』シリーズなどでは主人公がひたすら自分自身を痛めつけるように傷だらけになる姿にカタルシスをおぼえる。それは彼らが自分自身の罪を意識し、自分自身を痛めつける行為が贖罪になっているからだ。一方で、『ジョーカー』のアーサーには罪の意識がない。アーサーは幼少期に虐待を受け、社会からも冷たく扱われてきた。アーサーを一人の人間としてみた場合、自由意志懐疑論者としても、彼にすべての責任を負わせることはできないと思う。しかし、アーサーというキャラクターは、妄想にふけって他者を傷つけながら、悪いのは自分じゃないすべて他人が悪いのだという他責思考を象徴しているのかもしれない。現実を突きつけられ、看守から性的暴行を受け心を折られる姿は痛ましいが、その姿にカタルシスを覚えることはない。
もしかしたら映画の終盤でジョーカーよりも正気でいることをを選んだアーサーには、贖罪のチャンスがあったのかもしれない。しかし映画のラストでその可能性も断ち切られてしまう。慰めも救いもなく、ジョーカーであることも奪われ、何者でもない、ただ苦しむためだけに生まれてきたような人生を終える。
前作では”That’s Life”が皮肉な使われ方をしていたが、今作では”That’s Entartainment”がやはり皮肉な使われ方をしている。
A clown with his pants falling down
Or the dance that’s a dream of romance
Or the scene where the villain is mean
That’s entertainment!
ズボンがずり落ちるピエロ、ロマンスの夢であるダンス、意地悪なヴィラン……『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』にはすべて揃っている。しかし映画的快楽を禁止するこの映画では”That’s entertainment!”という歌詞が空しく響く。しかもラストはアンハッピーエンドで、ハリウッド映画の王道であるエンターテインメントをことごとく否定する。
ギャグ・アニメや漫画では、ハンマーで殴られてもたんこぶができるだけ、せいぜい鼻血が出るくらいだし、ビルの屋上から落ちてもぺちゃんこになるだけで全身打撲で死んだりはしない。次の瞬間にはどんなケガも治っている。しかし、本作ではそんなスラップスティックを生身の人間が演じることになる。得意げになるジョーカーの頭にハンマーが振り下ろされる。ジョーカーは血まみれになって倒れる。もちろんそれをみた観客は誰も笑わない。『ジョーカー』『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』はすべりつづける哀しきピエロの物語なのだ。
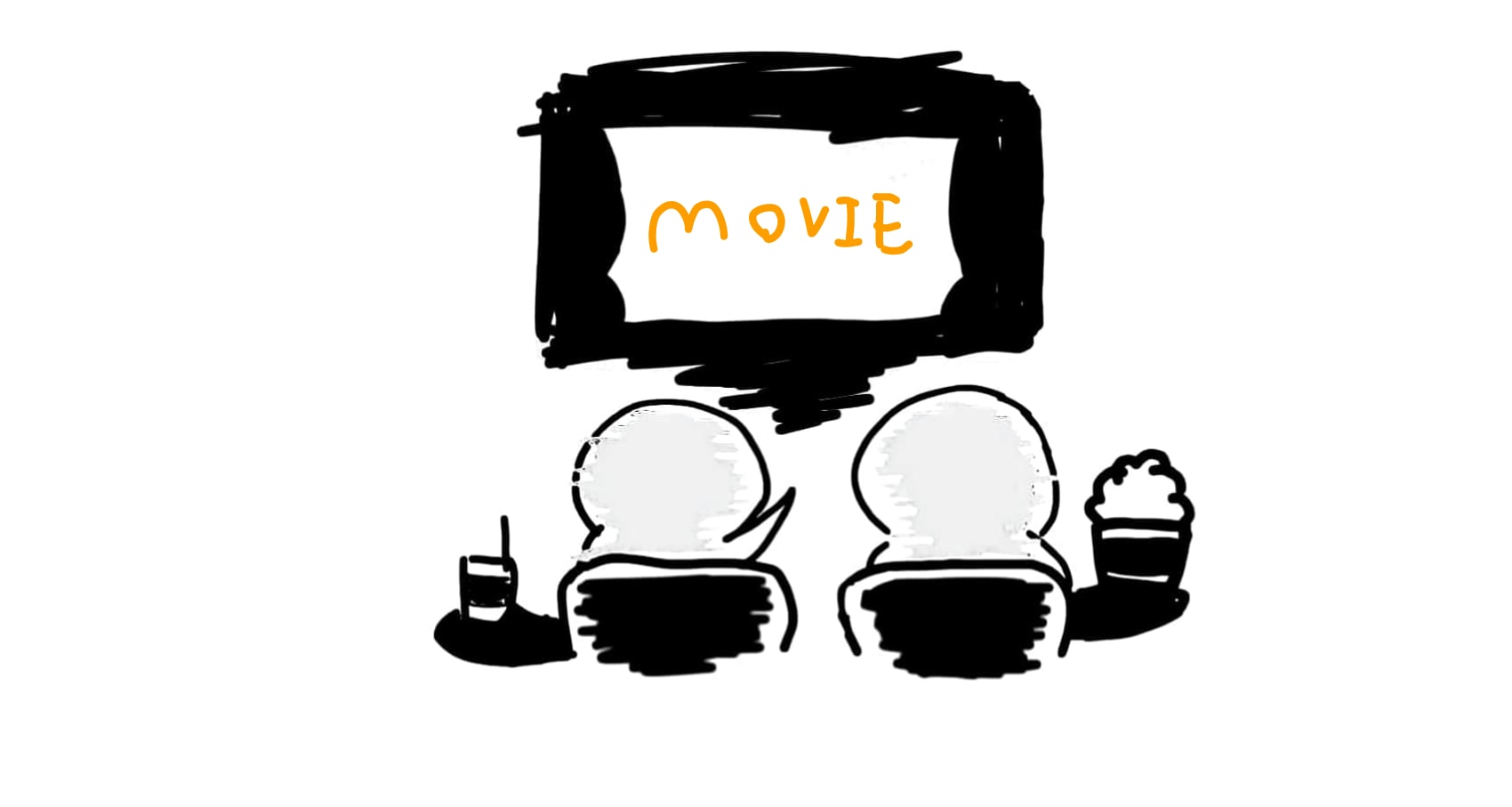

コメント