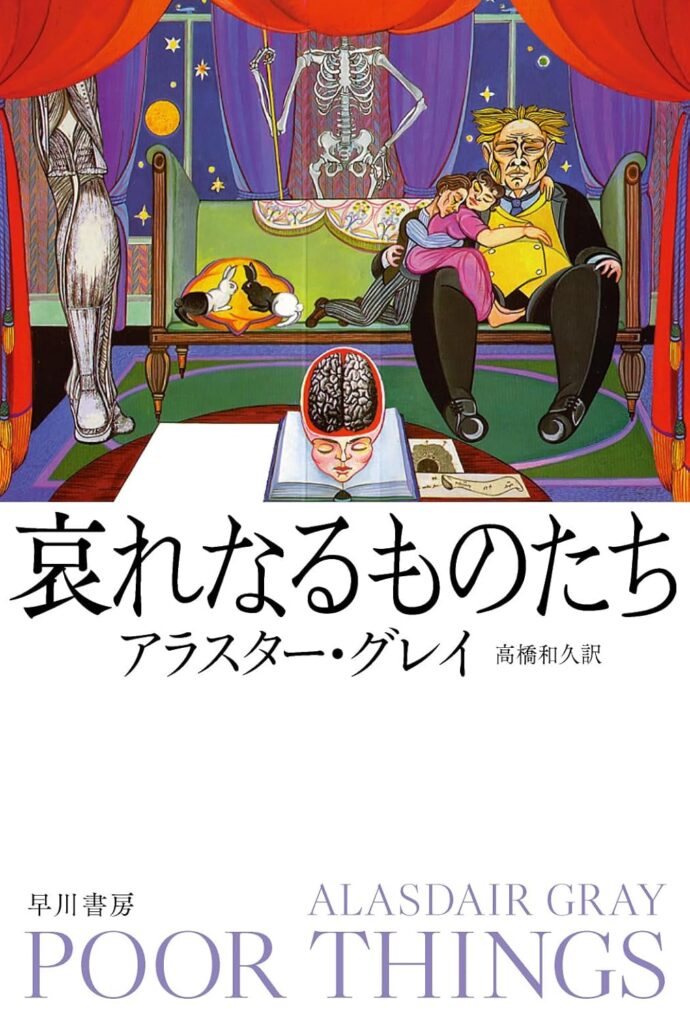
アラスター・グレイの同名原作小説を、『ロブスター』や『聖なる鹿殺し』のヨルゴス・ランティモスが映画化。
BORN SEXY YESTERDAY(無知でセクシー)?
主人公のベラ(エマ・ストーン)は最初、体は大人だが脳は赤ん坊の状態で、面白半分に皿を割ったり足でピアノを弾いたりしている。彼女の世話をしているのはマッド・サイエンティストのゴドウィン・バクスター(ウィレム・デフォー)。ゴドウィンはベラと学生のマッキャンドレス(ラミー・ユセフ)を引き合わせ二人は婚約することになる。
ベラの設定は、体は大人なのに心は幼いまま、性的にも無知で、それゆえに主人公の男性だけを愛するようになるという、都合のいいキャラクターかと思われるかもしれない。下記に紹介する動画では『フィフス・エレメント』などを例に、そのようなキャラクターを、”BORN YESTERDAY(世間知らず)”をもじって”BORN SEXY YESTERDAY”と名付けて論じている。
しかし本作の主人公ベラは、常識や男性から押し付けられる性的ファンタジー、社会から押し付けられる女性はこうでなくてはならないという規範をどんどんぶち壊していく。ベラの一番近くにいてサンドバッグのようにぼこぼこにされるのがマーク・ラファロ演じる弁護士のダンカンである。
ダンカンは女性を誘惑しては遊んで捨てるということを繰り返しているような男で、ベラのことも他の女性と同じように餌食にするつもりで駆け落ちをする。しかし逆にベラに魅了されたダンカンは、ひたすら自由にふるまうベラに翻弄され、身も心も財政状況もぼろぼろになっていく。ベラに「私のことを愛してるだろ?」と詰め寄るが彼女のほうは自分をなんとも思っていないことを痛感して、泣きそうになりながらかろうじて「カジノに行く」とだけ言うシーンのラファロの演技に、ざまあみろという痛快さと痛烈な哀れみが入り混じる。
原作との違い
原作ではベラの物語はマッキャンドレスの視点から書かれている。小説の最後でそれがメタフィクション的仕掛けによってひっくり返され、ダンカンだけじゃなくゴドウィンやマッキャンドレスもベラに対して自分勝手なイメージを押し付けているのではないか、と男性たちの視点を相対化していた。映画ではあくまでベラの視点から物語が描かれる。白黒だった映像がベラの成長にあわせてカラーになる。最初の駆け落ち先であるリスボンの現実とはかけ離れたシュールな街並みやベラの着ているドレスなど、奇妙な建物や衣装はこの映画がベラから見た世界であることを表している。メタフィクション的仕掛けがないかわりに、マッキャンドレスは原作よりも女性の主体性を尊重する男性として描かれる。ベラの意志を確認することを気にかけ、プロポーズの場面でもちゃんとベラの眼鏡にかなう受け答えをしている。
世界の美しさと醜さ、ベラが目指すもの
世界のすべてについて知りたがるベラは貪欲に知識を吸収し、驚くべきスピードで成長してダンカンを圧倒してしまう。船旅の途中、ハリーとマーサに出会い、哲学的な議論を闘わせる。ハリーはシニカルな現実主義者で、天真爛漫なベラに人類の醜さを教えるため、貧困の中で死んでいく赤ん坊たちを見せる。映画版でもそれを見てベラはショックを受けるが、原作では、最底辺の貧民たちにコインを投げそれを奪い合うさまを笑っている金持ちたちを見て、ベラは一時的に幼児退行を起こすほどのショックを受ける。
船から降ろされダンカンから独立したベラは、パリの娼館で働くようになり、同じ娼館で働く社会主義者でアフリカ系のトワネットと出会う。貧民たちの姿にショックを受けてなんとかしたいと願っていたベラが社会主義に興味を持つのは当然だ。売春は自立のための”生産”手段であり、貞淑であれという社会からの圧力や男尊女卑的な一夫一婦制へのカウンターにもなるが、全肯定されているわけではない。娼館の中で女性に選択権はなく、性が商品化され搾取されている状況も描かれる。
男女の権利、権力の非対称性、金持ちと貧民の経済格差、世界の美しさと醜さを知って落ちこむベラを娼館の女主人が励ます。女主人は娼婦たちを褒めたり脅したりしながら働かせ儲けている、搾取する側の人間でもあるのだが、いまはいちばん暗い時代でいずれは明るい時代がくる、そのために絶望せず進み続けろとベラを鼓舞する。
「哀れなるものたち」とは誰のこと?
まずは主人公たち、実験体として生み出されたベラ、追い詰められ自ら死を選んだヴィクトリア、父親の実験台になっていたゴドウィン、ベラに翻弄されるダンカンやマッキャンドレス。ベラ/ヴィクトリアを支配しようとしたブレシントン将軍(彼の最終的な運命については、『ロブスター』の監督らしさが表れてる)。貧民と死んだ赤ん坊たち。娼館でしかたなく働く娼婦たち。上半身と下半身を入れ替えられたニワトリや犬などの動物たちを指しているのだろう。
ベラの視線は自分やまわりの人間だけではなく、社会や世界全体にも向けられている。女性を縛る鎖を引きちぎりリバタリアンとして自由を謳歌するだけではなく、世界をよりよくしようとする。
現実の世界には戦争があり、性差別があり、権力者たちは自分たちだけで権力を独占しようとし続けている。そんな世界で絶望せずになんとか前を向いて生きて行こうとするわれわれ観客や動物たちも”哀れなるものたち”だ。シニシズムに陥らず、世界を客観的にありのままに美しい部分も醜い部分も観察し、よりよくしようとするベラの痛快な姿が、われわれ観客を鼓舞し勇気づけてくれる。
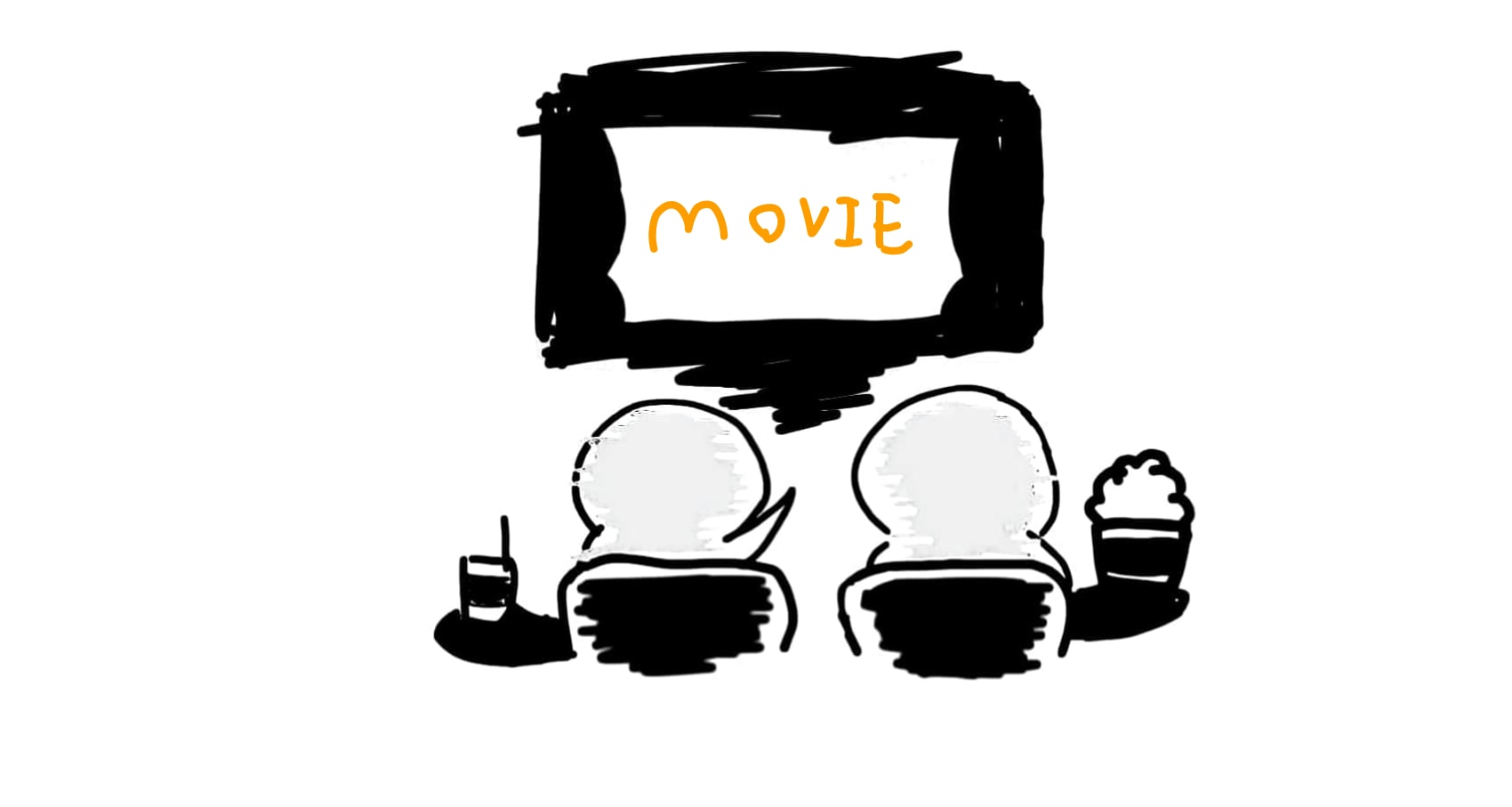


コメント