ドストエフスキーが『作家の日記』で書いているとち狂ってるとしか思えない政治評論にびっくりして、いろいろ調べてるうちに見つけて読んだ。ロシア思想史において「メシアニズム」と呼べる考え方を持っていた思想家を、列伝体のかたちで一人ひとり論じている。ソ連崩壊さなかの1989年に出版されている。
西欧のギリシャ・ローマ文化は現代(19世紀)においてすでに発達しきっていてこれ以上よくなることはなく、熟した果実のようにあとは腐り落ちるのを待っているだけであり、近代化には遅れをとったがそのぶん純粋で西欧のよい所だけを吸収できる若きロシアが西欧を補完することでヨーロッパをひいては全人類を救済すると、複数の思想家がまじめに考えていた。ドストエフスキーはよくロシア国民は全体が一人の人間のように一丸になって行動することができると書いてるけど、まさにロシアという聖なる光の巨人が、人類を補完し世界を救済すると本気で主張していたのだ。これってまるで『エヴァ』の「人類補完計画」じゃないか。『エヴァ』はキリスト教用語が大量に使われてるアニメだけど、ロシア・メシアニズムの影響が……? いや、それはないか……。
この本で論じられている「メシアニズム」とは、宗教的、あるいは民族的にロシアは救済者であるという考え方である。宗教的には原理主義的なロシア正教、民族的には汎スラヴ主義になる。
まず初めに、ロシア(当時のキエフ公国)がギリシャ正教を国教としたのが10世紀。その時点ですでに、対立するカトリックへの反発心が存在していた。
15世紀になって、ビザンチン帝国がオスマン・トルコに攻められ、ヨーロッパ諸国の援助を求めるためにローマ・カトリック教会との再統一を計画した。結局はギリシャ人信者などの猛烈な反対もあって統一は実現しなかったが、そのことがロシアの正教会信者の目には裏切りと映り、しかもその直後にビザンチン帝国が滅亡してしまったこともあり、真の純粋な正教会はロシアにしかないという考え、正教の教えを裏切れば国が滅亡するという恐怖が芽生え根付いていった。宗教的選民意識と民族的選民意識が同一視されるようになる。
17世紀、ポーランド王国にモスクワを占領されたりした結果、ロシア正教会の儀式のやり方などが混乱していた。混乱を解消するためギリシャ正教のやりかたに統一しようとするが、分離派は死をも厭わないような猛烈な反発をする。ロシア正教こそが第三のローマなのであり、裏切り者であるギリシャ正教に従えば世界が滅びると考えたから。
話はそれるけど、ロシア正教分離派はロシア語で「ラスコーリニキ」で、『罪と罰』のラスコリニコフと関係あるのかなと調べてみたら、モデルになった事件の犯人が分離派信徒だったらしい。犯人が純粋なロシア正教を残そうとした分離派信徒だったことで、さらに強く印象に残ったということがあったのかな。
ロシアの正教こそが純粋で真のキリスト教の教えを保持している。
そのようなロシア正教を敬虔に進行するロシアの民衆こそが選ばれた民である。
西欧は確かにわれわれより進んでいるが腐敗している。いまが絶頂であり没落する運命である。
ローマ・カトリックが西欧とともに滅びれば、人類を救済するキリストの教えはロシア正教だけとなるのだから、ロシアが西欧ひいては全人類を救わなければならない。ロシアの滅亡は世界の終わりである。
ロシア正教原理主義的なメシアニズムをまとめると上記のようになるだろうか。
一方、汎スラヴ主義的なメシアニズムは、スラヴ人はカトリック国やイスラム教国に住んでいたり、独立した国であってもロシアのような強大な国は存在しない。スラヴ民族を保護し導けるのはロシアしかない。西欧はスラヴ人を憎んでいるから対決は避けられない、となる。
冷戦時代の東西の対立は共産主義と資本主義の対立だったわけだけど、西欧への反感、敵意、ライバル視というのは近代化が始まった時からすでに存在していたのだな。だからソ連が崩壊しても西欧との対決姿勢は変わらなかった。
18世紀の後半には西欧を憧れだけでなく批判的に見るようにもなる。西欧文化の欠点。後発であるロシアの利点。19世紀になって、ナポレオンを撃退し、ロシアも国際政治で鍵を握るような立場になる。ヨーロッパの運命はロシアが握っている、世界史の舞台で偉大な役を演じられると考えるようになる。
国家というのは、侵略すれば領土を拡張できる、資源が獲れる、制海権を確保できる、という誘惑に常にさらされているものなんだろう。ロシアの場合、それがコンスタンティノープルという誘惑だった。ナショナリストは国益のために占領せよ、正教原理主義者はロシア正教を守るため、民族主義者はバルカン半島などのスラヴ民族を解放し彼らの盟主となるため、それぞれ南下政策を主張した。それぞれは独立しているけど、方向はみなコンスタンティノープルを指し示す。この三者の突き上げや誘惑に負けて戦争を始め、その代償を払うことになる。クリミア戦争、露土戦争、そして現在のウクライナへの侵略。これはロシアだけじゃなく、第一次、第二次大戦のときのドイツや大日本帝国も同じだったんだろう。もちろん政治力学にはもっと複雑な要素があってこんなに単純なものじゃないだろうけど。
第13章はまるまるドストエフスキーの政治思想に割かれている。『作家の日記』がきっかけで読み始めた本なので、やはりこの部分がいちばん興味深い。晩年に書かれた『作家の日記』だけでなく、『罪と罰』を書く前の流刑時代に書かれた手紙にも選民的な思想が現れているのは驚きだった。ドストエフスキーにとっては、真のキリスト教であるロシア正教の信仰こそがなによりも尊い。であるならば、最終章で紹介されているベルジャーエフのように、ナショナリズムや反ユダヤ主義に反対する平和主義者であってもおかしくないのに、実際はそうではなくかなり好戦的である。これは、ドストエフスキーが夢想家ではなくてある意味でリアリストだったからだと思う。ローマ・カトリックは堕落していてローマ正教だけが人類に残された唯一の希望であり、近いうちに西欧との決着をつける世界戦争が現実に起こると信じていたからこそ、領土の拡張やリアルな戦争を支持したのだ。ロシアが真のキリスト教の盟主になるにはコンスタンティノープルを自分のものにしなければいけない。それは理想論とか宗教的な次元の話ではなく、現実に起こらなければならない、だから現実の軍隊が実際に進軍する必要があるのだ。
ロシアの思想史には古代から現代まで脈々と「メシアニズム」の考え方が流れているのがよくわかるが、本書の「はじめに」でも書かれているように、ロシアやロシア国民の行動はすべて「メシアニズム」に基づいているとか、他国の行動の意図を説明するのに単純な陰謀論で判定したりとか、そういうための本ではない。それをしてしまえばドストエフスキーと同じ過ちをすることになる。
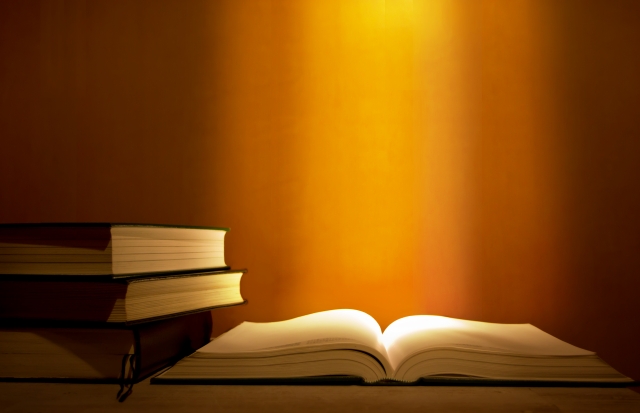


コメント