『作家の日記』を読んできて思ったことは、ドストエフスキー作品の理解に『作家の日記』は欠かせないということ、ドストエフスキー自身の帝国主義的な考え方へのむかつきと、ロシア民衆ひいては人類が救われなければならないという切実で純粋だけど完全に非現実的な希求への憐憫、それから政論と未来の予測が皮肉なかたちで実現したことへの空しさ。
「あの連中は、間もなく何もかも終わりになるとは思っていないんだ……あの連中の進歩やお喋りが終りになるとは思ってもいないんだ! あの連中はアンチ・キリストが生まれて……こっちへやってくるのに気づきさえしないんだ!」
『作家の日記6』(ちくま学芸文庫)p.328 漆原隆子「構想における『作家の日記』の役割」
彼はまるで恐ろしい大秘密を私に知らせるような表情を声にも顔にもあらわして言った。ついで、素速くわたしを一瞥すると、きびしい口調でたずねた。
「ぼくの言うことを信じますか、信じませんか? さあ、どうです、信じるか、信じないか、言ってごらんなさい。」
「信じますわ、フョードル・フョードロヴィッチ。でも、あなたは夢中になっていらっしゃるから、自然と誇張していると思いますの……」
彼はわたしが震えあがったほど強く机を叩くと、お寺の屋根の尖塔に立った回教の坊さんのように叫ぶのだった
「アンチ・キリストがやって来る! アンチ・キリストがやって来る! 世界の終わりはさし迫っている。世間のひとが思っているよりずっとさし迫っているんだ!」
この激情、まるで怒鳴るように議論する『罪と罰』の登場人物そのままだ。
巻末に収録されている漆原隆子「構想における『作家の日記』の役割」で、『作家の日記』に掲載された短篇「おとなしい女」について論じられていて、主人公の男は民衆から離れたインテリ層のことであり、最後に聖像を抱いて投身自殺する妻は民衆のことであるというのは、『作家の日記』を読んだ後ではもう、ちょっとこの読み方以外はできそうにない。
1880年8月号は、プーシキン記念講演についての解説と講演内容の原稿、そして講演に対する批判への反論である。講演の中でドストエフスキーは、プーシキンについて論じながら、ロシア民衆の特別さ、ロシア民衆の精神は世界のあらゆるものに興味をもち、人類の中でロシア人だけがそれらをすべて差別することなく受け入れ、人類愛によって全人類をまとめることができると語っている。ドストエフスキーのプーシキン論がどれくらい正鵠を射ているのかはわからないが、失神者も出たという聴衆が熱狂したのは、プーシキン論そのものよりも、以前から何度も語られているロシア民衆精神の特別さと、そのロシア民衆の精神によって達成される「全人類のハーモニー」という目標についてだったのだと思う。
講演に対する批判への反論の中でドストエフスキーはヨーロッパの現状について、
教会とキリストを抜きにしてヨーロッパで建設された蟻塚は(なぜならば、教会はその理想を曇らせて、もうずっと以前からいたるところで国家に変貌してしまったからである)、もうとっくの昔にその道徳的根源が根本からぐらぐらになり、なにもかも、普遍的で絶対的なものをすべて失ってしまい、――この建設された蟻塚は、わたしはあえて言うが、もうすっかり土台を侵食されてしまっている。第四階級の足音が聞こえ、早くもドアを叩いて中へ押し入ろうとしている。もし開けてやらなかったなら、ドアを叩き破るにちがいない。第四階級はこれまでの理想などはほしいとも思わず、既存の法則をすべて拒否している。妥協したり、譲歩したりすることはないので、ちょっとした突っかい棒などでは建物を救うことはできない。譲歩はただ火に油をそそぐにすぎない。第四階級はすべてを手に入れようとしているのである。誰ひとり考えも及ばないような、そんな事態がやってくるに相違ない。
『作家の日記6』(ちくま学芸文庫)p.123
工場や銀行は、ちょっとでも戦争が長引くか、あるいは長引きそうな気配が見えると、たちまちどれも閉鎖されてしまうだろう。そうなると職を失った数百万のプロレタリヤは、空き腹をかかえて街頭にほうり出されることになる。しかしあなたは政治家の思慮分別に期待をかけて、彼らはいくらなんでも戦争を起こすようなことはあるまいと思っておられるのではないだろうか? しかしそんな分別に期待をかけることのできた時代がこれまで一度でもあったろうか? それでなければ議会に望みをかけて、彼らは戦争の結果を見越して、戦費を出すことはあるまいと思っているのではないだろうか? しかし議会が戦争の結果を見越して、指導的人物にちょっとでもねばられた場合戦費の支出を拒否したことが、これまで一度でもあったろうか? さてそこでプロレタリヤは街頭に出た。彼はこうなってもこれまでどおり、飢えて死に瀕しながらも辛抱強く待っているだろうと、あなたはお考えだろうか? 前とちがって政治上の社会主義が現れた、インターナショナルが組織され、社会主義の国際会議が開かれ、パリ・コミューン事件のあったあとなのである。いいや、こんどはこれまでのようにはならないだろう。彼らはヨーロッパに向かって飛びかかり、古いものはすべて永遠に破壊してしまうに決まっている。
『作家の日記6』(ちくま学芸文庫)p.125-126
ドストエフスキーの予言はほとんど当たった。ただ、30年後、第一次大戦の影響で庶民の生活が苦しくなり、社会主義によって体制が打倒され革命が起こったのは、ヨーロッパではなくロシアだったというところだけが違っていた。なんという皮肉だろう。ロシア民衆の中にあるキリスト教精神による全人類の救済はそれから150年経っても実現していないどころか、まったく正反対のことが起こっている。
目の前に分かれ道がある。片方は西欧と同じ方に向かう道、片方はキリスト教精神に導かれる道。ドストエフスキーやアメリカのキリスト教福音派の人たち、宗教右派と呼ばれる人たちは、一人ひとりが敬虔になり道徳的に生きれば犯罪もなくなるし経済さえよくなると考えている。指導者たちがみな聖人になり、国民全員がどんな罪も犯さなくなったとしたら、たしかにその国は理想郷となるだろう。でも歴史上そんな国は存在しなかったしこの先も実現しないだろうと思われる。しかし彼らに言わせれば、西欧のリベラルな政治、法律、科学にしたって同じじゃないか、犯罪や貧困、悪政を根絶できていないしこれからもできないだろう、どちらが正しい道かは誰にもわからないではないか……。ドストエフスキーはもちろんキリスト教精神の道を選ぶだろう。目的地まで何百年かかろうと、到着までに何千万人が死ぬことになろうと、そうでない道はそれ以上に時間がかかりそれ以上の人間が苦しみ死ぬだろうからである。150年後に生きるわれわれは分かれ道の先がどうなったのか知っている。それが究極的に正しかったのかどうかはわからないが。
『作家の日記』で論じられることのほとんどはドストエフスキーの独創ではないしロシアだけに特有のものでもない。ロシア・メシアニズムを唱える思想家はロシア思想史には連綿といるし、ナショナリズムはどの国にもある。反エリート主義的だったり既存の科学知識を否定する陰謀論。「いまにみてろ、すぐにも世界がひっくり返るようなことが起こるから」という終末論的態度などなどは現代にも生き延びている。そういう人たちの根底にあるのは純粋だけど見当違いな善意と、ひとりよがりの希望、破滅への恐怖だ。
最後の発行となる1881年1月号の前半では、当時のロシアの財政問題とその解決方法を提案している。まず財政問題を無視すること。インテリ層と民衆との結合。民衆の中にある聖なる原理を信頼すること。そうすれば財政問題も解決される。ドストエフスキーにとっては、農民である民衆が近代化によって貧農から脱するのではダメなのだ。なぜなら近代化とは西欧化であり西欧化とは無神論化だから。無学で野卑な民衆、何世紀ものあいだギリシャ・ローマ文化と比べられるような文化とは無縁で農奴として生きてきた民衆、彼らには正教の教え以外には何もない。それがロシアの民衆を特別なものにしているのだ。しかも、ローマ・カトリックが堕落して国家権力と一体化してしまったいま、キリスト教の純粋な教義はロシアにしか残されていない。正教だけがこの世界に救いをもたらすのに、ロシア民衆が西欧化されてしまえば、つまりは世界は闇に包まれることになる。唯一の正しい理念はロシア民衆の中にあるのであり、権力者やインテリ層は民衆に従うことでしかロシア社会を正しく導くことはできない。
後半はロシアとアジアについて。ヨーロッパに向けた政策は行き詰っているので、いったん背を向けてアジアに進出するべきだと説いている。ヨーロッパに対してはへりくだってきたが、アジアに対しては主人としてふるまえると書いているのは、帝国主義の考え方とはこういうものかと腹が立つが、この20年後日露戦争に敗れることになるのを思うと、腹立ちよりも憐れみをおぼえる。日露戦争に勝利したもう一方の帝国もドストエフスキーの主張をそっくり裏返したような形で中国や東南アジアを占領し、満州事変で国連を脱退、太平洋戦争に突入して、帝国の運命は破滅することになる。道を誤った帝国たちに歴史の皮肉と残酷さを思うとただ悲しく空しい。
政治評論家としてのドストエフスキーがトンデモなことを信じていたということではない。西欧を模倣する近代化によって病んで苦悩するインテリ、カトリックの陰謀、ロシアの民衆精神による全人類の救済……『地下室の手記』も『罪と罰』も『カラマーゾフの兄弟』もこのような考えに基づいて書かれている作品なのだ。
1881年1月号の刊行直前にドストエフスキーは肺気腫により60歳で死ぬ。
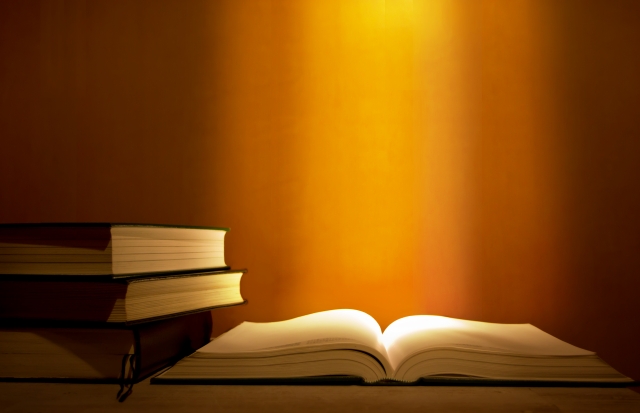


コメント