なんのためか? より高い、偉大な生活を送るため、偉大な、無私無欲で清らかな理念によって世界を照らすため、究極的に諸民族の有効的な団結という強力で偉大なオルガニズムを具現し創造するためである。このオルガニズムを政治的弾圧や剣によらずに、信念と、模範と、愛と、無欲と光明によって創造すること、それにもう一つ、これらのいと小さきものたちを自分と同じ高さに引き上げ、その母親としての使命を彼らに理解させること――これがロシヤの目的である。
『作家の日記5』(ちくま学芸文庫)p.386 小沼文彦訳
人類共通な普遍的な理念によって、ロシア人だけでなく人類は救済されないければならない、という思いが根底にあるのはたぶん間違いないと思う。自分も含めた人類が……ということなのかもしれないけど。
近代化、産業革命、資本主義でヨーロッパ中、農奴解放されたロシアも貧富の格差や社会的混乱にみまわれた。フランス革命もヨーロッパ中を巻き込んだ大混乱を引き起こし、市民が皇帝を処刑するというまさに天と地をひっくり返し、社会主義と人権思想を生み出したけど、普仏戦争ではフランスは敗れることになった。ドストエフスキーによれば、ローマ・カトリックは堕落し衰弱して、世界を支配しようと陰謀を巡らしている。ドイツはプロテスタントだからダメ、つまりは西ヨーロッパはどこも絶望的で、正教のロシアだけが唯一希望のある大国なのだ。
ドストエフスキーにとってはこれは夢想や理想論ではなく、現実に起こらなくてはならないことだった。だから露土戦争も肯定するし、コンスタンティノープルはロシアが占領しなければならないと激しく主張する。そうでなければ絶望しか残らず人類は永遠に苦しみ続けることになる。こういナショナリスティックな陰謀論含みの主張だけ取り出せば、いまのネトウヨyoutuberそのものだ。
『日記』には「モスクワ報知」という新聞の記事もときどき引用されてるんだけど、その論調をみると、ドストエフスキーの国際政治観とか陰謀論めいたところも、彼独自のものではなかったらしい。「モスクワ報知」は保守的な編集方針だったっぽいけど。『日記』の7・8月号では、トルストイの『アンナ・カレーニナ』の結末について批判していて、そこで引用される露土戦争における国民の愛国的行動を称揚し擁護するキャラクターの論調はドストエフスキーの論調そのままだ。だから当時の世論もドストエフスキーの主張と似たり寄ったりだったのかもしれない。
ロシア・メシアニズムという思想もあって、聖なるロシアという考えもドストエフスキーの独創というわけではなさそう。
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%EF%BD%A5%E3%83%A1%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%BA%E3%83%A0-1217705
ドストエフスキーはこんなことを文字通りに信じていたんだろうか。第1次、第2次大戦、その後の歴史を知っているわれわれからすると、まったくありえないとわかっているけど、国民国家というものが誕生し始めた時代、150年前のこととはいえ、無私無欲な国家というものが現実に存在しうると信じられたんだろうか。それに、150年後にロシアが侵略戦争をしているという皮肉もある。
皮肉といえば、ドストエフスキーによればフランスで生まれた社会主義や人権思想は、神を信じないキリスト教であるらしい。ローマ・カトリックの力が衰えたせいで生まれたもので、近代化や科学や資本主義と同じく、社会主義も人類を救うものでないと批判している。しかし、その30年後、革命によってロシアは世界初の社会主義国になるのだ。
『作家の日記』を読むとわかるのは、ドストエフスキーが停滞した社会や不健康な若者たちを憂慮していること。『罪と罰』を読んだとき、ラスコーリニコフはまさにニーチェのいう超人で、太陽に近づきすぎたイカロスみたいに結局は墜落するけど、道徳に挑戦し超人になろうとする姿に力点があるのかと思ってた。しかし『作家の日記』を読むと、いっけん知的で正常に見えるけど、内面は病んでいるような若者を憂慮しているのがわかる。そんな作家が書くものは、超人になろうとすることより、そういう病んだ魂がいかに救われるか、あるいは救いがないかに力点があることになるけど、『作家の日記』を読むまでは逆だと思っていた。『罪と罰』も『地下室の手記』もまともな小市民的な登場人物はほとんど登場せず、作品の大部分で描かれるのは主人公がひたすらもがき苦しむ姿で、『地下室の手記』の主人公はまったく救われないし、『罪と罰』も救済は唐突で付け足しのように思える。小説から受ける印象と『日記』の印象はまったく違う。
日記と『作家の日記』――ドストエフスキーにおける事故物語の問題――
https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/38171/files/SLA0270002.pdf
この論文からの孫引きになるけど、
読者は、フィクションの中であらゆる絶対的権威の概念を否定し、異なる諸世界観の相互作用を明らかにしている同じ作家が、『日記』では絶対的権威を振り回していることに驚かざるをえない
まさにこういう驚きがある。
(西欧諸国は)ロシヤによって掲げられた、ありとあらゆる理念の中で最も偉大な理念の、偉大な、神聖で、この世で見たことも聞いたこともない旗じるしを認めることはできないであろう。そうした理念があればこそ人間は生きているのであって、それがなければ、もしそうした理念が人類の中で生きつづけることをやめたならばーー人類は硬化して感覚を失い、不具になり、厄病にでも取りつかれたように虚脱して死んでいくことになるのだ。
『作家の日記5』(ちくま学芸文庫)p.379 小沼文彦訳
『カラマーゾフの兄弟』で次男のイワンは次のような議論をしたとして紹介される。
人間が人類を愛さねばならなぬという自然の法則など全く存在しない。かりに地上に愛があり、現在まで存在したとしても、それは自然の法則によるのではなく、もっぱら人間が自分の不死を信じていたからにすぎないのだ。その際イワン君が括弧つきで言い添えたことですが、これこそ自然の法則のすべてなのだから、人類の抱いている不死への信仰を根絶してしまえば、とたんに愛だけではなく、現世の生活を続けようという生命力さえ枯れつきてしまうのだそうです。それどころか、そうなればもう不道徳なことなど何一つなくなって、すべてが、人肉食いさえもが許されるのです。しかも、これでもまだ足りずに、この人は結論として力説したのですが、たとえば現在のわれわれのように、神も不死も信じない個々の人間にとって、自然の道徳律はただちに従来の宗教的なものと正反対に変わるべきであり、悪行にもひとしいエゴイズムでさえ人間に許されるべきであるばかりか、むしろそういう立場としては、もっとも合理的な、そしてもっとも高尚とさえ言える必然的な帰結として認められるべきなんだそうです。
『カラマーゾフの兄弟』(新潮文庫)p.165-166 原卓也訳
ドストエフスキーの作品、とくに『カラマーゾフの兄弟』は『作家の日記』を読まずには語れないんじゃないだろうか。
ドストエフスキーの独特な……というか、150年後のいま読むとどうかしてるとしか思えない国家観や外交や戦争に対する意見については、ほとんどこの本で(未読で目次を見ただけだけど)ツッコまれてるっぽい。

第1章 ドストエフスキー対トルストイ
第2章 民衆への同情が『悪霊』を導く
第3章 ドストエフスキーとロシア民衆
第4章 ドストエフスキーの見たロシアの近代
第5章 近代を乗り越えてゆくロシア
第6章 ドストエフスキーの戦争論
第7章 コンスタンチノープル領有論と反ユダヤ主義
第8章 スラブ主義の思想家―ホミャーコフとダニレフスキー
第9章 ドン・キホーテとジョルジュ・サンド
第10章 プーシキン記念講演と世界の調和
やっぱり19世紀末、20世紀初頭というのは近代の始まりだったりジャンル小説としてのSFができたりとか、様々なものがいまあるかたちになり始めた時でおもしろい。19世紀の世界史も勉強したくなるし、『ドストエフスキーの戦争論』も読みたいけど、そうなると何冊読まないといけなくなるか……。まずは最終巻である『作家の日記6』を読んでしまおう。



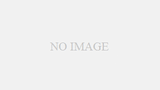
コメント